「週案書くのに、時間がかかりすぎる~!」と嘆く新人保育士さん、たくさんいますね。
私も新人の頃は、週案書くのに1~2時間とかかかってました。
しかも、ひとり担任だったから、それが毎週の重圧…。
でも、週案なんて書き方のコツさえ覚えてしまえば、30分もかからずに書くことができます!
保育歴15年の私は、10分か15分で書き終えます。
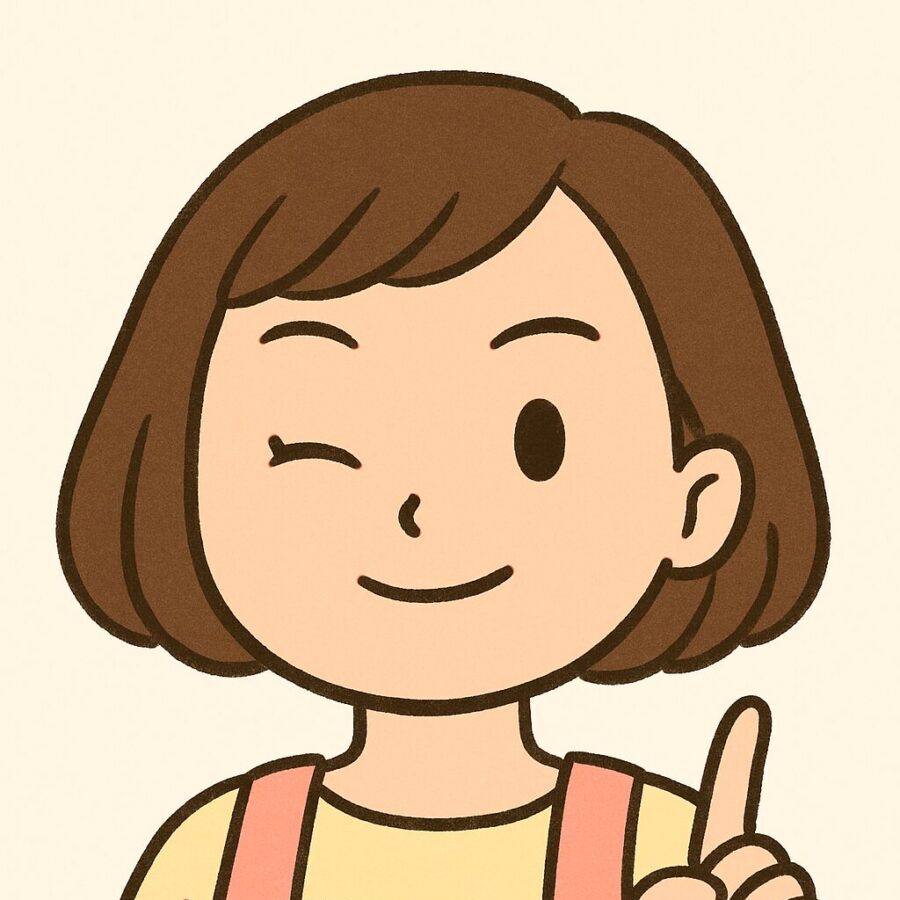 くぅ
くぅもちろん書いた後に、再度、頭の中で整理する時間はとりますよ~
週案を書くのが毎週億劫になっている保育士さんのために、さくっと書ける週案の考え方とコツを徹底解説しちゃいます!
週案を書く前にしておくと時間短縮できること


週案をスムーズに書くために、事前に必ずしておくべきことがあります。
年間・月案の確認
週案は、年間指導計画と月案を細かくしたものであるので、月のねらいはきちんと理解しておきましょう。
そのねらいをもとに、そこから内容がずれないようにすることが大切です。
クラスの現状把握
本やネットで、「〇月〇週目の週案」など、検索すると例文はたくさん出てきます。
しかし、きちんとあなたのクラスの子どもたちの現状を把握しておくことが、何より大事です。
生活リズム(食事・着脱・排泄など)
友達関係や活動への集中度合
季節や行事の影響(運動会練習中、発表会前など)
これらをもとに、子どもたちの様子や成長過程で、やるべきことを決めましょう。
先週の振り返り
先週の活動を振り返り、できたこと・できなかったことを把握しましょう。
出来なかったことは、再度活動に取り入れることも大事です。
同じやり方でやるのか、別の活動として取り組むのか、そこを考えることが必要ですね。
子どもの姿や反応を思い出し、反映させましょう。
新しい活動を取り入れることも大事ですが、反復して行うことが必要なものもあります。
そこを、よく見極めましょう。
週案を書きやすくする3つの視点


週案の書き方の視点を明確にしておくと、「何を書いたらいいのか…」と悩む時間がなくなり、作成時間が短縮できます!
①ねらい設定は、週のメイン活動を決めてから照らし合わせる
月のねらいを達成するには、どんな活動をすべきなのかを想像します。
週のメイン活動を設定してから、季節なども考え、週のねらいを決めると比較的スムーズに考えられるはずです。
②活動は、代替え案やもう一つのサブ的活動を考えておく
週案を書くには、メイン活動の他に、サブ活動を考えておこう!
下記のものを、まずは考えてメモしておくと、週案を書くのがとてもスムーズです!
メイン活動 4つ
前週の反省を活かした活動 1つ (なければメイン5つでもOK)
サブ活動(天候に左右されないもの) 2~3種
★の活動を月から金曜日の予定に振り分け、☆活動は短時間で終わりそうな日に振り分けて書く。この型があるだけでも、時間は短縮にできますね。
前週の反省点は、必ず反映させましょう。そして、その反省をもとに活動を考えるのが鉄則です。
サブ的活動まで予定していた日に、主活動だけで終わってしまったら、それを翌日のサブ的活動にすればよいのです。
また、天候に留意して活動設定することが望ましいので、週案を立てるのに天気予報は必見ですね。
そして、天候に左右されない活動案を、考えておくことも必要ですね。
これを考えておくと、「え?今日雨なの?どうしよう…何やろう…」と焦ることがなくなります。
③週案は、自分の頭の中を整理するためのものと考える
週案は、あくまでも、自分の頭の中を設計図化したものです。
だからこそ、自分でパッと見てわかる書き方でいいんです。
でも、組んでいる先生にも自分のやりたい活動が伝わらないといけません。
自分の中で整理したものを、きちんと見える化するように心がけましょう。
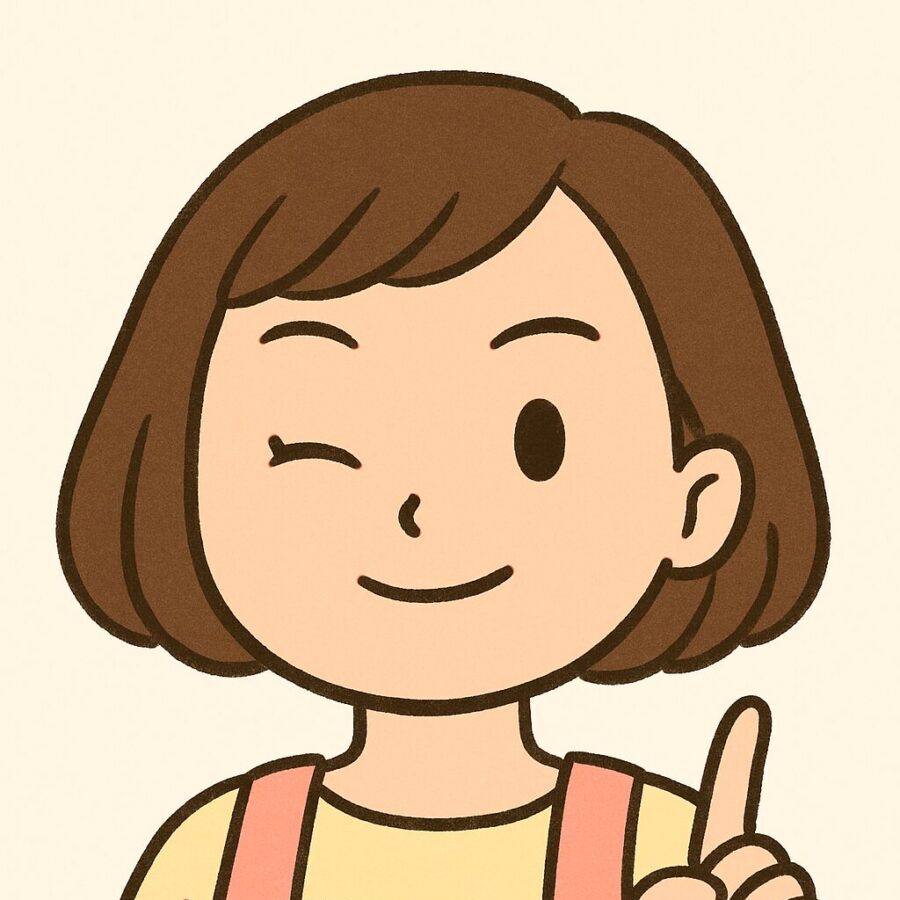
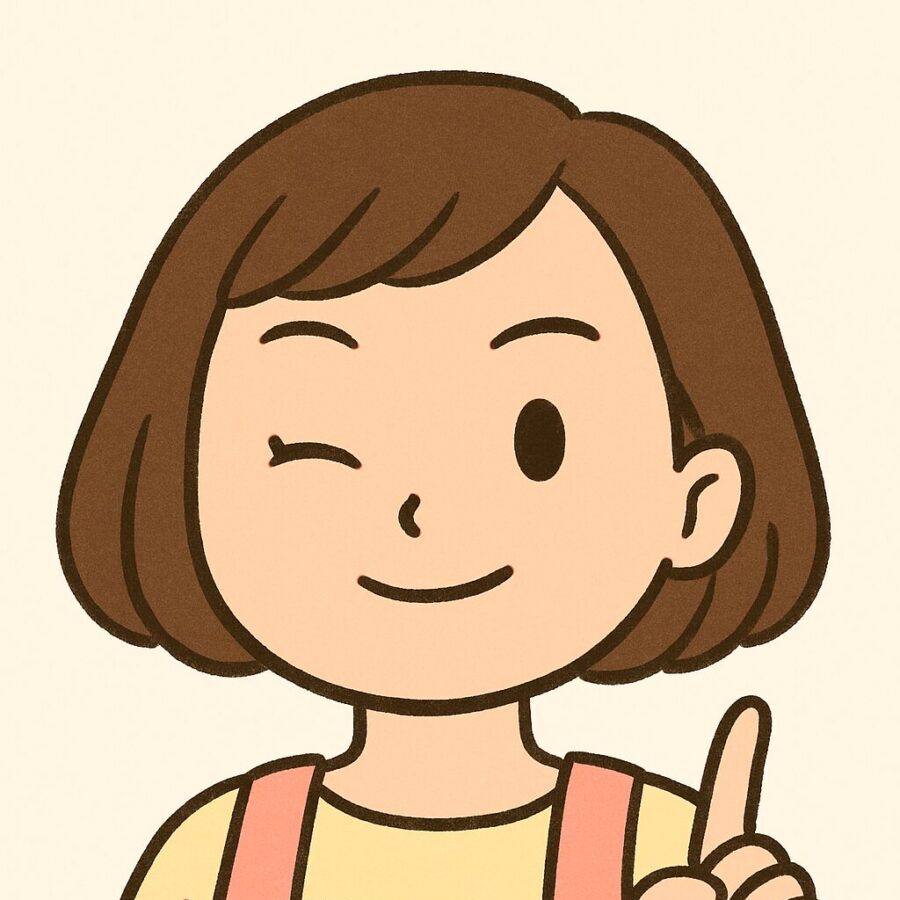
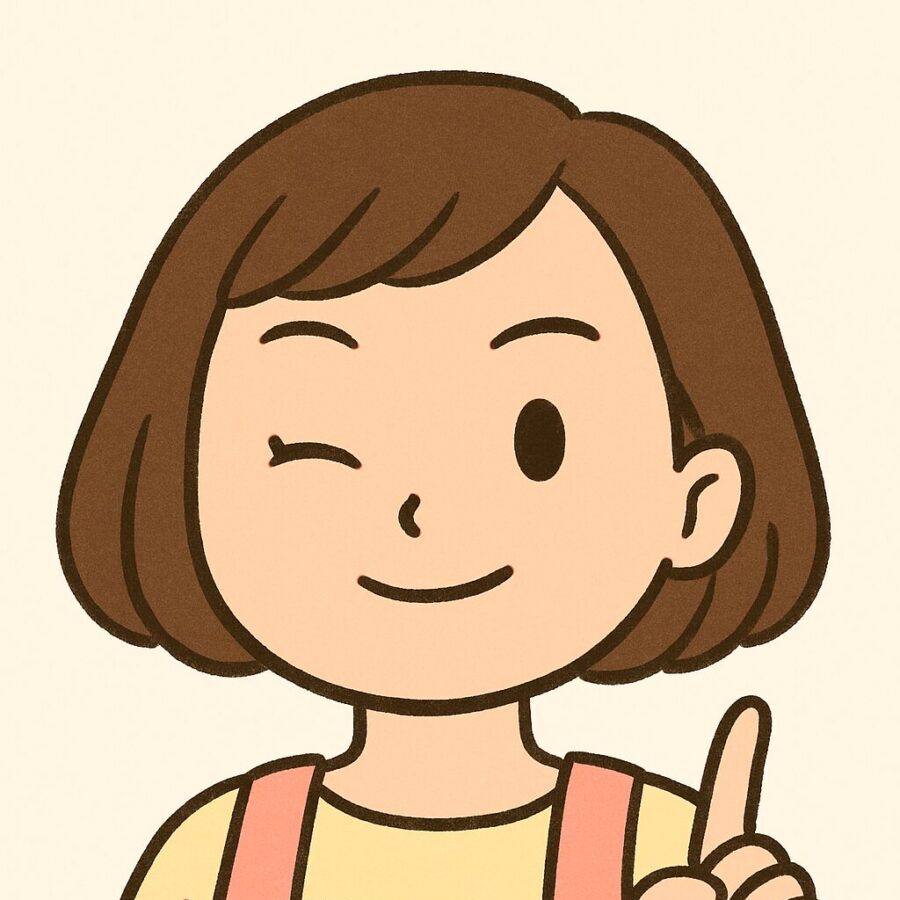
もちろん、子どもたちが楽しく安全に過ごすための計画であるということを、忘れてはだめですよ~!
週案の項目ごとの書き方と考え方のポイント
園によって様式が違うと思うので、テンプレではなく、項目ごとの書き方と考え方のポイントを紹介します。
この考え方を理解すると、かなりの時短となります。
ねらい設定
ねらいは、子どもの発達や興味に合わせることが大前提となります。



私は、月案を踏まえた上で、週のメイン活動を決めてから、ねらいを考えることの方が多いかな~
ねらいは、短く明確なものにするのが理想!
欲張るとややこしくなるので、注意が必要ですよ。
活動からの狙い設定は、邪道だという人もいるかもしれませんが、この考え方でねらいの設定の仕方を覚えていくのがスムーズです。
② 子どもの活動・ 計画案・姿
主活動をメインに書く園が多いと思います。
園行事があれば、まずはそれを記入します。
そこから、一週間の流れをよく考え、「製作・運動・遊び」をバランスよく設定するとよいです。
季節や天候に合わせて、柔軟に変更できる内容にしておくと対応しやすくなります。



私は、だいたい1日に1つの主活動のみを書いておくよ。
でも、一つだけの活動では時間を持て余しそうな内容の日は、別の活動も考えておくとスムーズに保育できますね。
なので、1週間の中で、主活動の他に、サブ的な活動を3つくらい考えておくといいと思います。



製作は、3日にわけて行うこともあるよ~
③ 配慮事項・保育士の関わり
この項目は、子どもが活動をするにあたって、保育士の関わり方や注意すべき点を書きます。
保育士の視点から書くことが大事です。
「怪我事故のないように遊ぶ」では、子ども視点となりますね。
などが、保育士が配慮すべき点での正しい書き方となります。
『活動を安全にすすめる上で、気をつけるべきポイント』を考えると、いいですよ。
④ 材料・準備物
活動をするにあたって、準備するもの、必要なものを記入する項目です。
自分の中で前日までに揃えるべきものをリスト化しておきます。
そうすることで、当日の活動をスムーズに行うのに、忘れものを防ぐことができますね。
頭の中で、その日の活動をイメージし、必要なものをすべて書き出しましょう。
⑤ 振り返り欄・反省・気づいた点
これは、作成段階では書きません。
1日を終えるたびに、この下記の視点を意識し、振り返りましょう。
予定したことが、きちんとできたのか。
準備不足はなかったのか。
子どもたちの発達に合っていのか。
この3つを“保育士の視点”から、反省すべき点・良かった点を書いておくのがいいです。
次に活かすための、大切な記録となります。
また、チーム保育としての共通の財産にもなりますので、きちんと書き留めることが大事です。
週案の書き方|発達に合わせた週案の視点~3・4・5歳児~


年齢別に、発達段階を理解しておくと、活動の設定もスムーズになります。
クラス全体の姿にも、しっかり目を向けることも大事ですね。
3歳児
3歳児は、まず基本的生活習慣の自立が大きなテーマです。
とはいえ、生活習慣そのものを”主活動”として週案にいれるのは少し難しいですよね。
そんな時は、配慮事項の中に生活習慣を自然に取り入れることをおすすめします。
たとえば、「戸外遊び」の日の配慮事項に、こんな分を入れられます。
・汗や服の汚れに自分で気付けるよう声をかけ、着替えを促す
・スムーズにできない子には援助しながら、自分でやろうとする意欲を育てる
また、3歳児はまだ集団行動に慣れる段階なので、活動は短め&繰り返しを意識します。
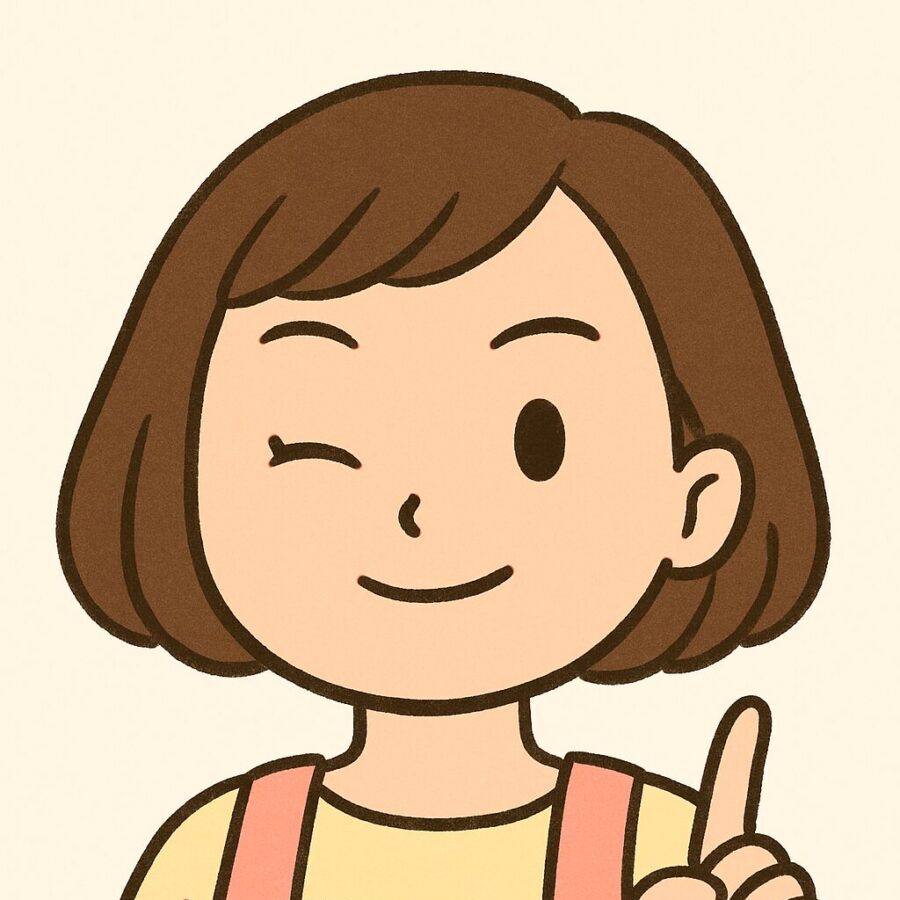
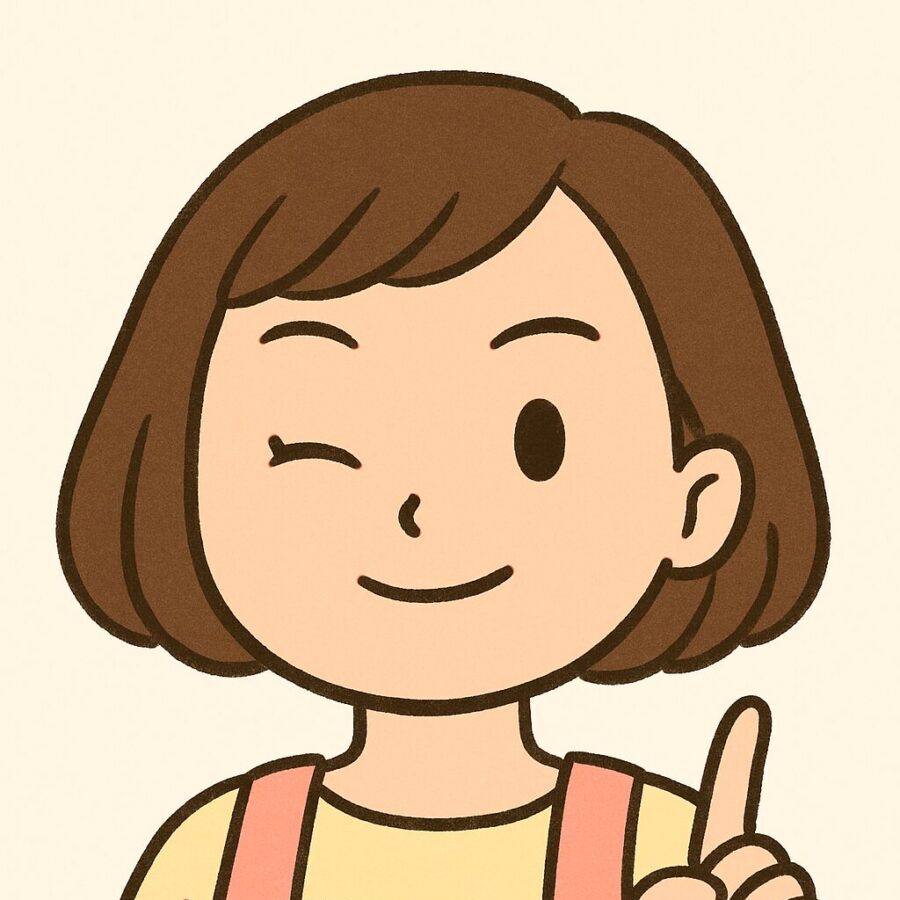
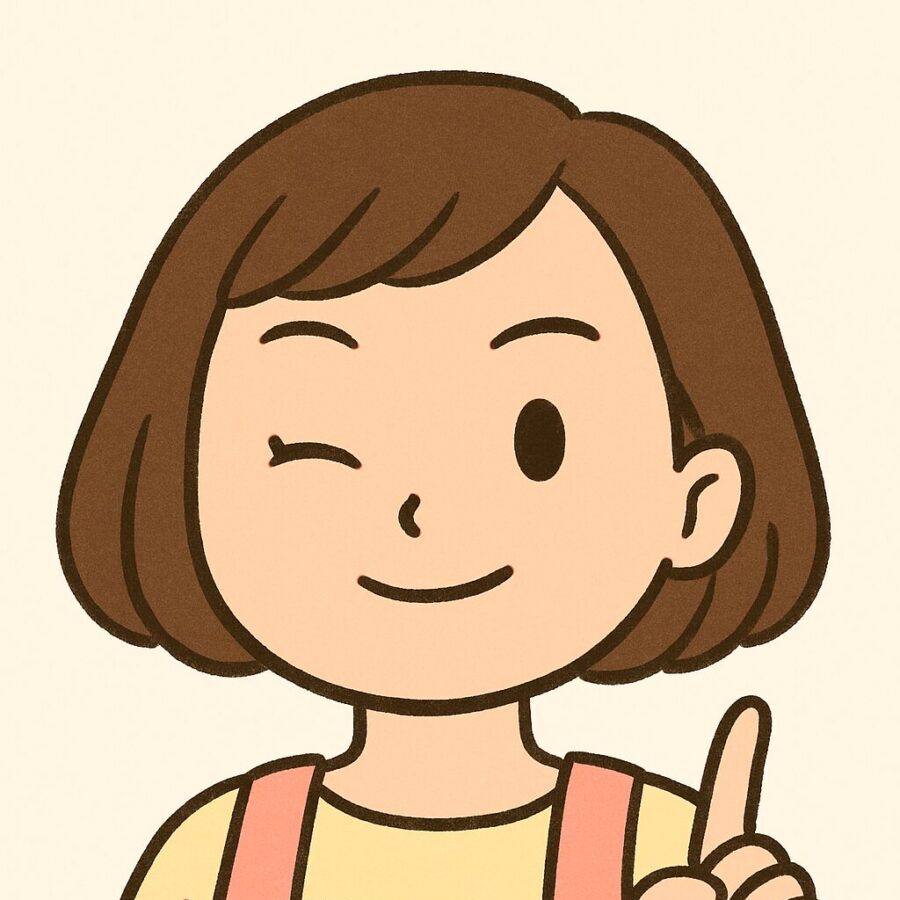
ただ同じことを繰り返すのではなく、少しずつレベルを上げていくのがポイントだよ。
さらに、言葉や気持ちの表現を促す活動も効果的です。
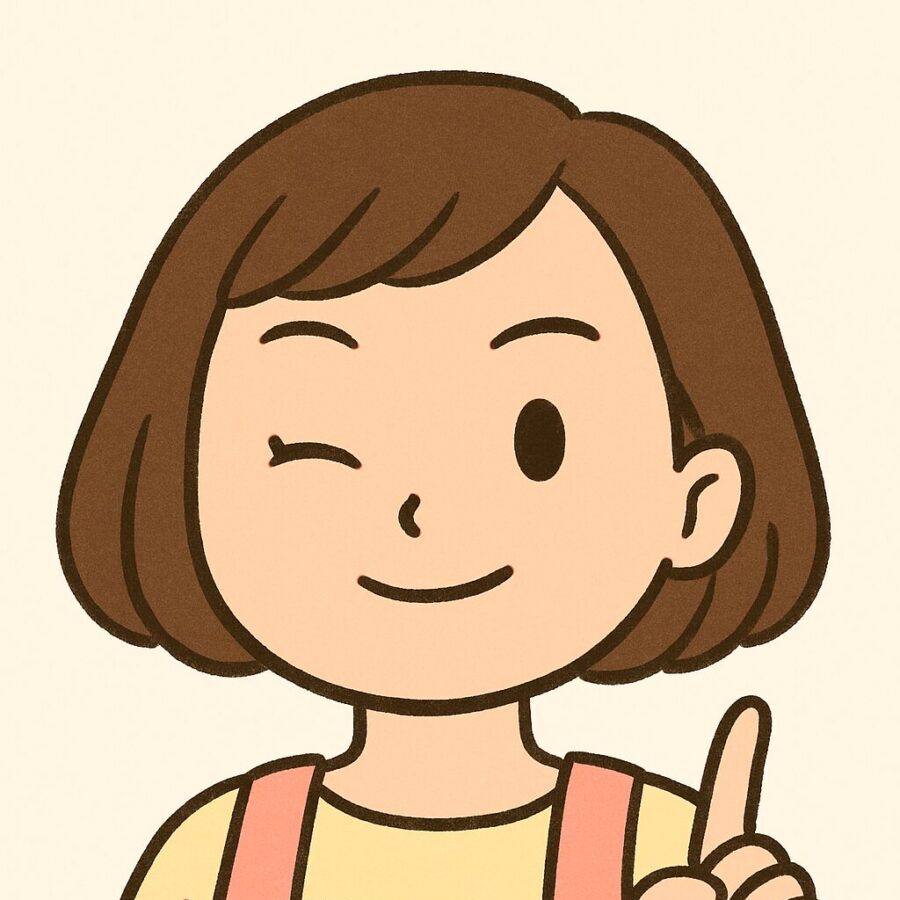
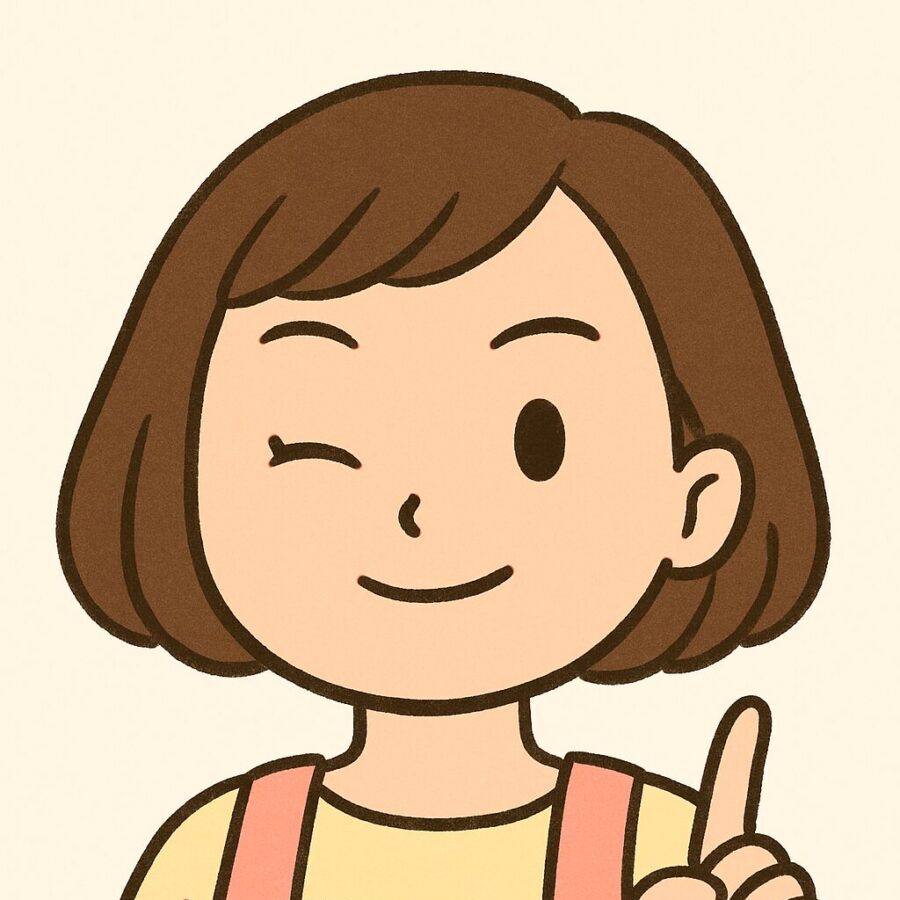
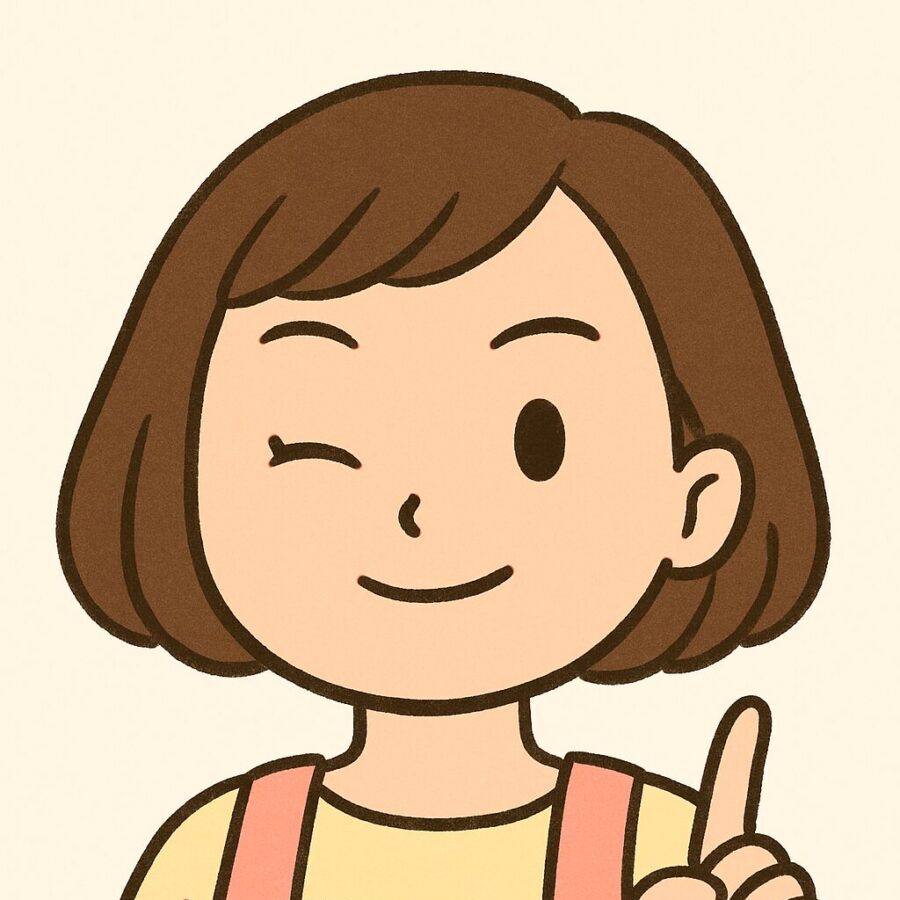
おままごとや、ごっこ遊び、経験したことを話せる時間をを多く取り入れ、声を引す場を作ってるよ。
4歳児
4歳児は、協同性が芽生え、育つ時期です。
グループ活動やグループ製作など、「一緒にやる」経験をどんどん増やしていきましょう。



大型製作など、楽しんでやれるようになるよ。
想像力を広げるためには、ごっこ遊びを展開させたり、製作で自分なりの工夫を取り入れられる活動もいいですね。
また、集団でのルール意識を高めるために、ルールのある集団遊びを多く取り入れることも大切です。
5歳児
5歳児は、就学を見据える時期。
1年間を通して、次の3つの力を育む活動を意識します。
役割分担を与えて責任感を持たせたり、自ら見通しを立てらるよう導きます。
活動の目標やねらいを理解させ、達成感を味わえる経験をたくさん積ませましょう。
まとめ
週案は、書き方のコツさえ覚えてしまえば、さくっと書くことができます。
子ども目線なのか、保育士目線なのかえを、よく考えて書くことが大事ですね。
週案作成は、自分の頭の中で1週間を事前に整理する作業です。
まずは、自分で考え、整理する意識を持ちましょう。
きっと、今までよりも時間短縮され、かつ分かりやすい週案が書けますよ!
▶「週案っていらなくない?」と思う保育士さんは、こちらの記事も合わせてお読みください。
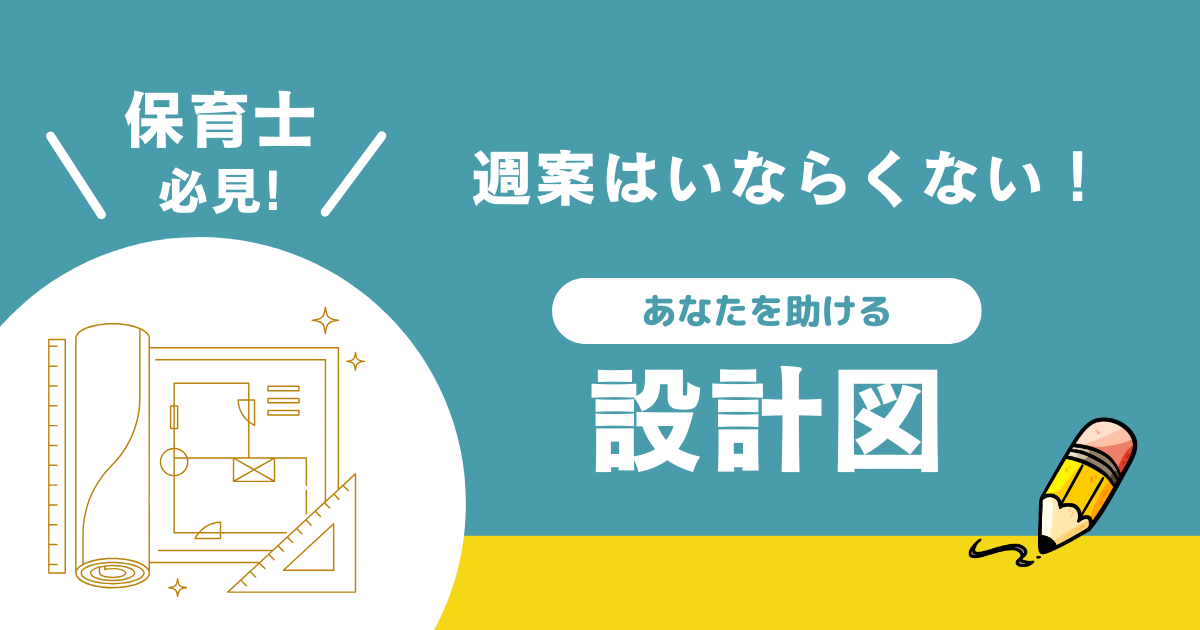
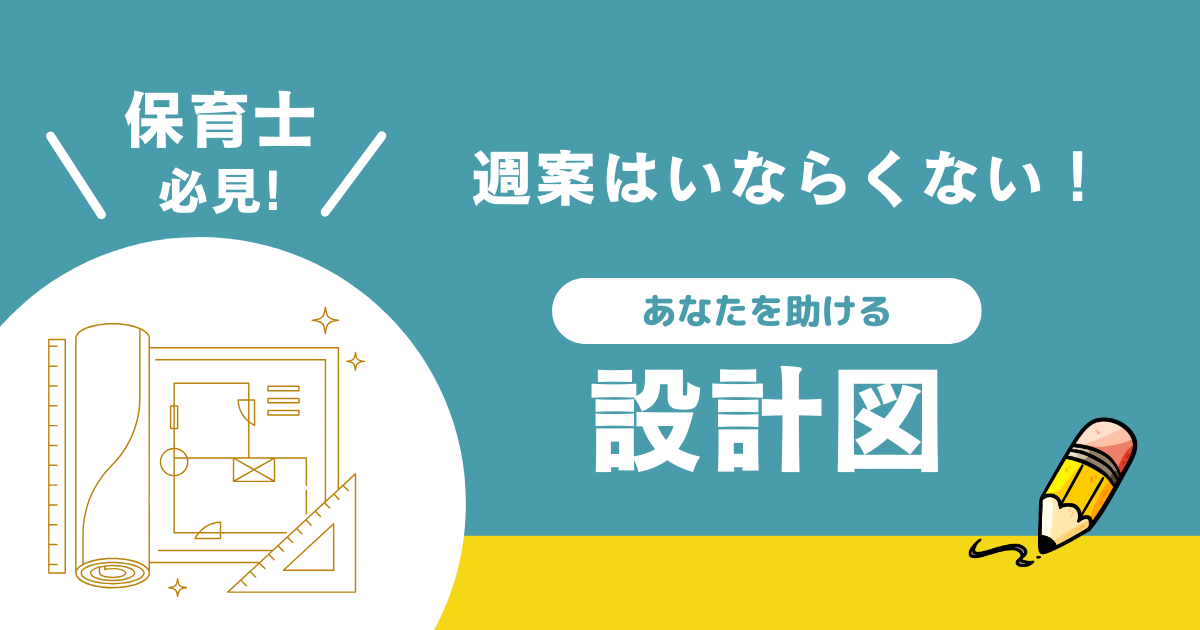
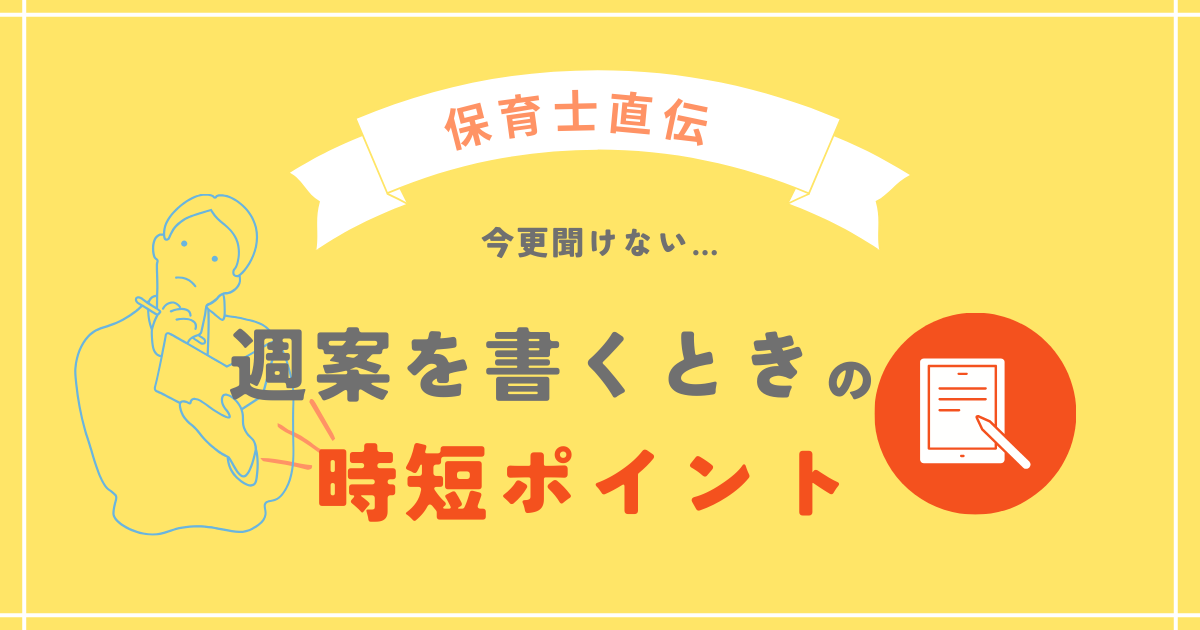


コメント