「発表会、配役決めが憂鬱…」
「毎回、なかなか決まらないのなんで?」
発表会の配役を決めるときって、本当に悩みます。
「希望が優先?」「バランス重視?」「主役は誰にする?」
どんなに経験を重ねてたって、こればかりは毎年の悩みどころです。
配役決めは、子どもたちの成長を引き出す大事なきっかけ。
だからこそ迷うし、慎重にもなるんですよね。
この記事では、子どもたちが自分で「やりたい!」と思える配役の決め方のコツについて話します。
配役決めの考え方や、子どもたちとの関わり方をまとめました。

題材選びとクラスの雰囲気が、配役を左右する
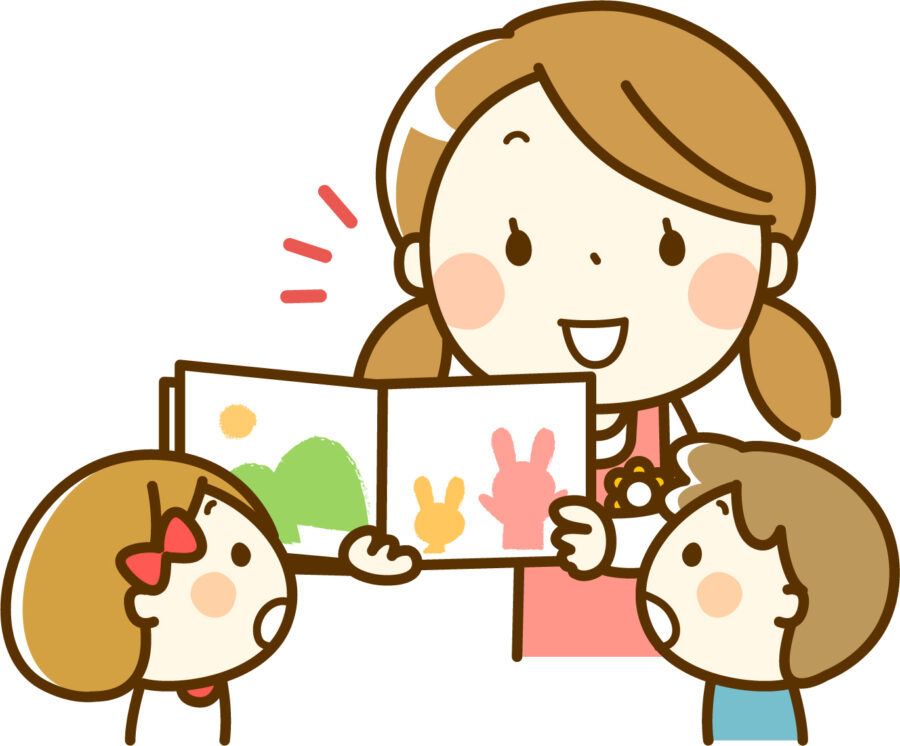
まず一番重要なのは、題材選びです。
どんな題材にするかで、クラス全体の方向性がほぼ決まります。
最近では、男女で役を分けない流れも増えてきています。
男の子が「おばあさん役」、女の子が「鬼役」なんてこともよくあるんです。
性別ではなく、子ども一人ひとりのやってみたい気持ちを軸に考えるのがいいでしょう。
とはいえ、男女の比率やクラスの雰囲気によって、自然と役が偏ることもあります。
そのときは、雰囲気をよく観察して、全体のバランスをとるようにしましょう。
題材は、それぞれが自分らしく輝ける内容であり、クラス全員でやり遂げられることが大切です。
園の決め方を理解した上で、自分の中に基準をもつ
幼稚園・保育園によって、
・1役1人
・1役複数人
・希望そのまま
など、配役の決め方がさまざまです。
「桃太郎10人に対して鬼1人!」なんて園もあるほど。
どんな人数設定でも大切なのは、子どもたちが納得しているかどうか。
担任の仕事は、「どうすれば全員が納得して取り組めるか」を考えることです。
配役は「与える」のではなく、「一緒に決める」ことが大事。
その意識を持つだけで、子どもとの関わり方が変わります。
配役は「主役=いい役」ではないことを共有しよう
配役を決める前に、子どもたちにそれぞれの役柄について話しておくことが大切。
それは、「主役が一番いい役」ではないことを理解できるようになるからです。
劇には、登場するすべての役が必要となります。
もちろん主になる役がいて、その役を支える大事な役があって、敵になる役があるから話が面白くなる。
その役すべてがあるからこそ、劇ができる。
「どの役も大切で、みんなが主役なんだよ。」
そんな言葉を、何度でも子どもたちに伝えてあげましょう。
配役決めは希望とバランスのさじ加減が難しい
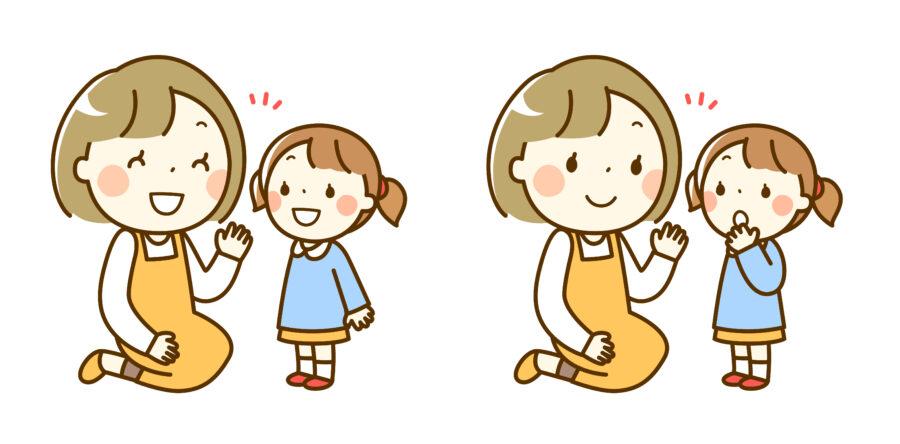
配役を決めるとき、必ず出てくるのが希望の偏り。
「人気の役が集中する」
「静かな子がセリフの多い役を希望する」
など、ケースはいろいろです。
そんなときは、ひとりずつとよく話をして、気持ちを確かめましょう。
「主役をやってみたいけど心配…」
「本当は違うのがやりたかったけど言えなかった…」
など、子どもたちの中には、少なからず葛藤があります。
逆に、いつも頼りにしている子があえて控えめな役を選ぶことも。
そんなときは、どうして「その役を選んだのか」をしっかりと聞いてやることが大事です。
理由によっては後押しをしてやることも必要になります。その子の気持ちに寄り添えるよう裏でしっかりサポートしてあげましょう。
ただ、無理強いはNG。
でも、背中をそっと押してあげるべき時もあるんです。
子どもが「自分で決めた」と思える配役にしていくことが、何よりも大事ですね。
どの配役にも見どころをつくる演出を

いざ決まった配役を、どう活かすのかは担任の腕の見せどころ。
頼りにしている子ばかりが目立ってしまうと、全体のバランスが崩れます。
そんなときは、セリフを足したり、動きを変えたりして、見どころを散らしていきましょう。
短い出番の子にも、見せ場を。
それが、みんなで作り上げるうえでとても重要です。
全員でやり切ったとき、子どもたちの達成感が全然違ってきます。
全員が輝ける発表会は、先生の手でつくることができるんです。
保護者対応を見据えた、子どもとの関わりを
配役が決まると、保護者から質問を受けることもあります。
「どうしてこの役なんですか?」と聞かれたときに、 自信を持って答えられるようにしておきましょう。
そのためにも、配役決定後には、全員と個別に話す時間を持つのがポイントです。
ひとりずつ呼び出して、面談するのではありませんよ。
自由遊びの時間、給食を食べながら…など、子どもたちが素でいる時間に敢えて声をかけるんです。
「この役、楽しみ?」
「どうしてこれにしたの?」
そんな小さな会話を通して、子どもの納得具合を確認しておくと安心です。
全体の話し合いでは見えなかった気持ちが、その会話の中で見えることもあります。
そうした積み重ねが、保護者への説明にも自信を与えてくれるのです。
▶保護者が配役に不満に思ってしまう理由を詳しく書いています。これを知ると保護者と子どもたちとのかかわりも見えてきますので、合わせて読んでみてください。

まとめ|配役は「信じて託す」こと

発表会の配役は、先生が子どもに役を与えるのではなく、子どもの力を信じて託すことです。
どんな役であっても、子どもたちはその中でしっかり成長します。
挑戦し、迷い…その中でやり遂げる過程が、なによりの学びになります。
子どもの気持ちを尊重しながらも、クラス全体が輝くように調整する。
そのバランスを取るのが、保育士の大事な役割です。
みんなで一つの舞台を作り上げる喜びを、子どもと一緒に味わえる発表会になりますように。
今日も笑って、子どもたちと楽しい時間を過ごしてくださいね。
▶週案なんていならくない?!と思う保育士さん、ぜひ読んでみてください!
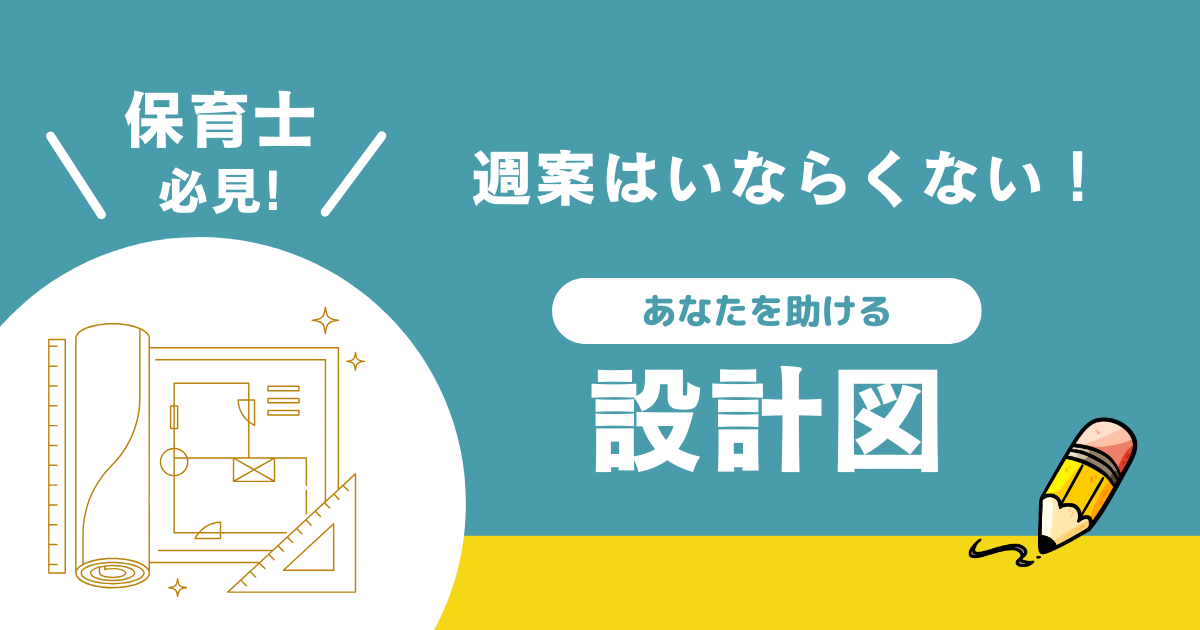

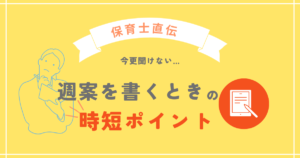

コメント