うちの子、お友達をたたいてしまうんです…
クラスにいる子が、毎日お友達をたたいてしまってトラブルになっている…
そんな風に悩んでいる、ママや新人保育士さん、多くいるのではないでしょうか。
自分の子が、他の子を傷つけてしまうなんて、親としてはショックですよね。
また、クラス運営する中で、毎日トラブルが続くのも大変。
でも、3歳児がお友達をたたいてしまうことって、珍しいことではないんです。
だからといって、ただ見守り、やめるのを待つだけでは、日々のストレスになってしまいます。
今回は、お友達をたたいてしまう子への対応方法。
そして、3歳児がなぜ、お友達をたたいてしまうのかの理由を、現役保育士のくぅがお話させていただきます!
「すぐにたたかなくなる」のは、無理だけど、もうどうしていいのかわからない…と悩むママや新人保育士さんの不安を解消しちゃいます。
3歳児がお友達をたたいたときの対応方法5選

お友達のことをたたいてしまうのを、やめさせたい!
どうしてもたたいてしまう子への対応方法を教えます。
寸止めで行動を止める(即効性あり)
お友達をたたこうとしたまさにその瞬間、腕をつかみます!
これが、一番即効性があります。
未遂で済むうえに、子どもにとっては、「え?」「は!」という気付きになるんです。
たたく瞬間、相手との距離をとるよう引き離したり、間に入ったりするのも効果的!
とにかく、「たたこうとしている、まさにその瞬間で止める!」
これが何より、たたくことをやめさせられる一番の対応方法です。
 くぅ
くぅこれは、保育園を巡回している障害児保育専門の先生からの教えです。
実際に、私もこの対応をして、たたくことが減った子どもを何人も見ています。
短く、明確に、注意する
子どもがお友達をたたくのを止められなかったときには、たたくことはいけないことだと、短く、明確に、そして毅然とした態度で伝えます。
「やめようね」
「たたいたら痛いよ」
「手は、たたくためにあるんじゃないよ」
そういったシンプルな言葉を選びましょう 。
ダラダラと注意するのは、逆効果です。長いお説教は、子どもには響きません。
理由を聞き、気持ちを言葉にしてあげる
まずは「どうしたかったのかな?」と、子どもの気持ちに寄り添いましょう。
「あのおもちゃが使いたかったんだね」
「仲間に入りたかったんだね」
「そこを通りたかったのね」
子どもの気持ちを、言葉にしてあげることが大事。
代弁してやることで、言葉で伝える力が少しずつ育ちます。
上から叱らない
「なんでたたくの!?」は逆効果です。
絶対に言ってはいけません。
たたいてしまった子どもを責めるのではなく、どうすればよかったのかを一緒に考えましょう。
お友達との関わり方を具体的に伝える
理由が聞けたら、その関わり方を伝えましょう。
「貸してって言ってみようね」
「そこ通ってもいいか聞いてみよう」
場面ごとの、お友達との関わり方を教えます。
「順番で遊ぼうね」
「こっちから行こうか」
代替となる行動を提案してみるのも効果的です。
【重要!】成長の過程として見守ろう
これらの対応をしたとしても、すぐにやめるさせることはなかなか難しいです。
しかし、繰り返し伝え、対応していけば、必ず伝わるときが来ます。
「たたかないようになる」ことが目標ではなく、「言葉で伝える力」を伸ばしてやることが、大切ですね。
▶親子でのコミュニケーションとして、一緒にアンパンマンを描いてみるのはどうでしょう?
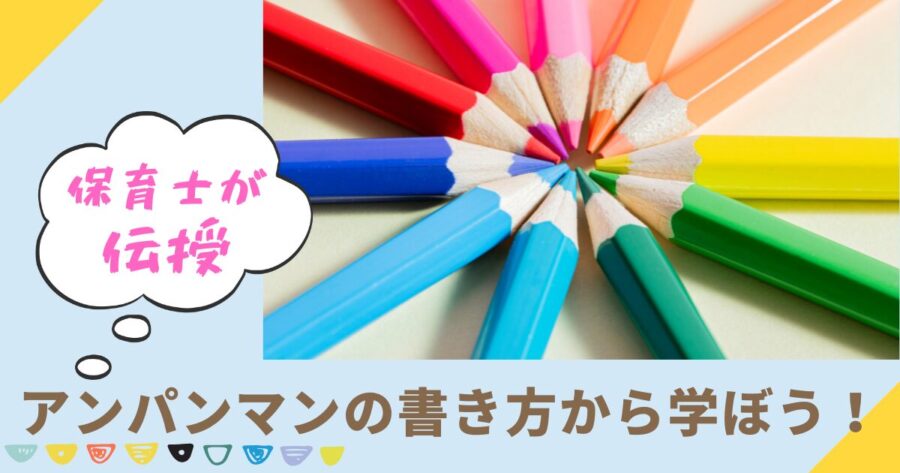
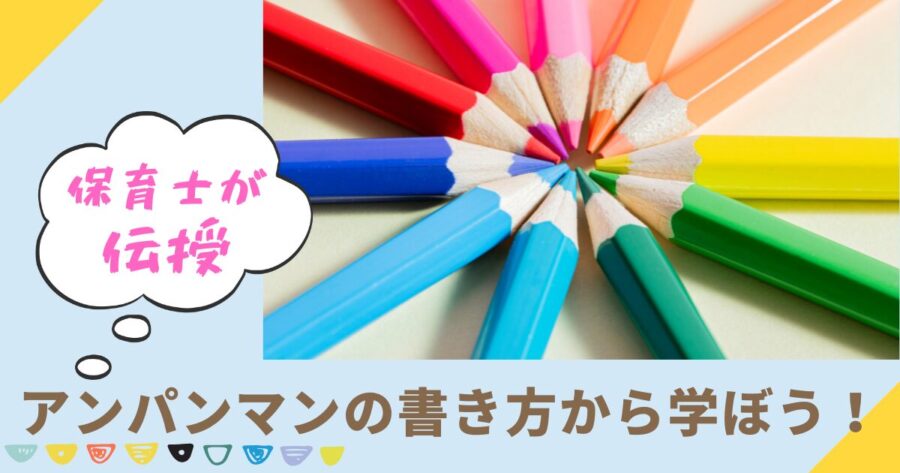
3歳児がお友達をたたく理由


たたく子には必ず事情があります。
なぜたたいてしまうのか原因を見極めるのがポイントです。
その見極めのポイントを、これからお話します。
理由① 言葉で伝えられないから
3歳児は、簡単な会話のやりとりがどうにかできるようになってくる時期です。
しかし、まだ語彙力の少なさ、表現力の未発達さが目立ちます。
自分の気持ちをうまく言葉にできないから、「いや!」「やめて!」の代わりに手がでてしまうんです。
3歳児にとっては、たたくことが自己主張の手段のひとつとなっています。
理由② 関わり方が未熟だから
3歳児は、まだ、友達との距離感をうまく取れません。
そして、自分の気持ちを押し通そうとする自我が強いです。
集団生活の中で、だんだんと社会性学び始めたからこそ起こる行動だとも言えます。
理由③ テリトリー意識が強いから
3歳児は、テリトリー意識が強く「ここは自分の場所」「邪魔された」と感じやすい時期でもあります。
急に自分のテリトリーに侵入されたような気がして、思わずたたいて妨害しようとするのですね。
特に集団生活に入り始めの子に多くいます。
理由④ 玩具は全部自分のものという感覚がある
3歳児は、物の所有の概念がまだ曖昧です。
兄弟がいれば話は別ですが、お家にあるおもちゃは、すべて自分のもの。
それが集団に入り、初めて「みんなのもの」を経験するのですから、違和感に感じる気持ちもわかりますよね。
「貸す」「順番で使う」の理解は、これから育つ段階となります。
理由⑤ 感情のコントロールが未発達だから
3歳児は、怒りや悔しさをうまく処理できず、すぐ行動に出てしまいます。
まだまだ、自分の気持ちをうまくコントロールできません。



泣く・叫ぶ・たたく、は子どもにとっては同じ表現手段なんです。
まとめ|対応を通して「言葉で伝える力」を育てよう


3歳児がお友達をたたくのは、未熟さゆえの自然な姿であって、異常ではありません。
ただ、「保育園で毎日のようにお友達をたたいている」なんて聞かされると、不安になりますよね。
家ではそんな姿はない子ほど「保育園で嫌な思いをしているのでは?」と心配にもなるでしょう。



3歳児がお友達をたたくことが続き、「発達の障害があるのかな…」と心配される方は、保育士に相談しましょう!
それがその子にとっての成長の過程であるのか、その特性があるのかは、普段見てくれている保育士がよくわかっているはずです。
もし保育園からお友達をたたいてしまって…という報告を受けたら、まずは相手の保護者にしっかり謝罪をすることが大切です。
子どもはまだ素直に謝ることが難しいので、大人同士の対応が今後の関係性も守ってくれます。
そして子どもへの対応は、「寸止め」「短い注意」「気持ちの代弁」の3つが効果的。
叱ることよりも、どう伝えればよかったのかを一緒に経験していくことが、成長につながります。
ママ・パパも、「たたいてしまうのは成長の一歩」と捉えて、安心して見守ってくださいね。
子どもの気持ちを理解しながら関わることで、少しずつ 言葉で伝える力 が育っていきます。
焦らずに、子どもとの関わりを楽しんでくださいね。
保育士のくぅが、お話させていただきました。
子育てって大変ですが、これからも一緒に成長していきましょ~♪
▶トイトレがなかなか進まないお悩みは、こちらの記事も合わせてお読みください。
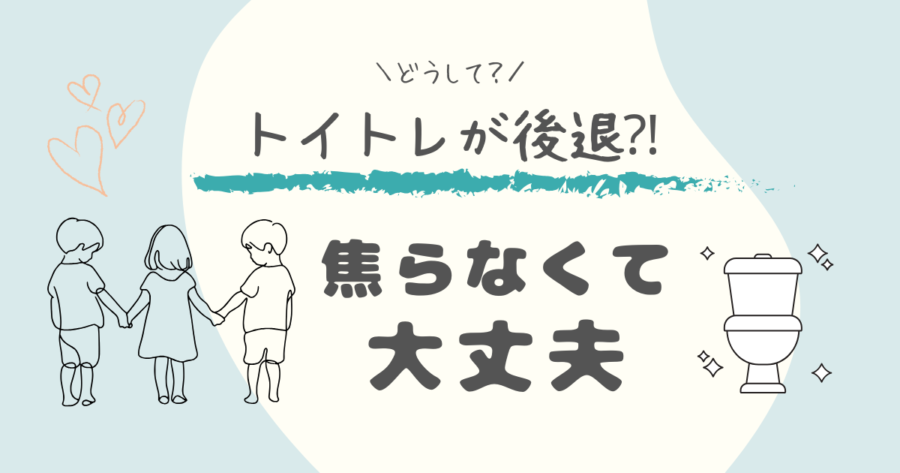
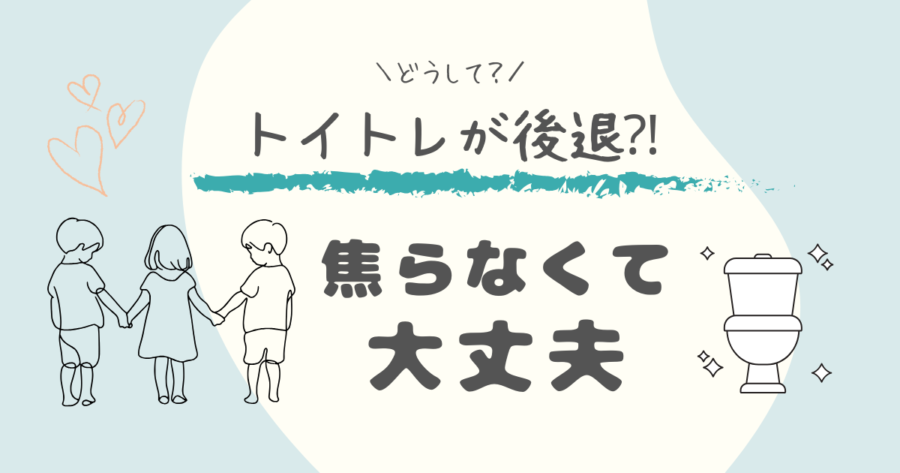
▶ごはんをなかなか食べてくれない子にお困りのママ・パパは、こちらも合わせてお読みください。


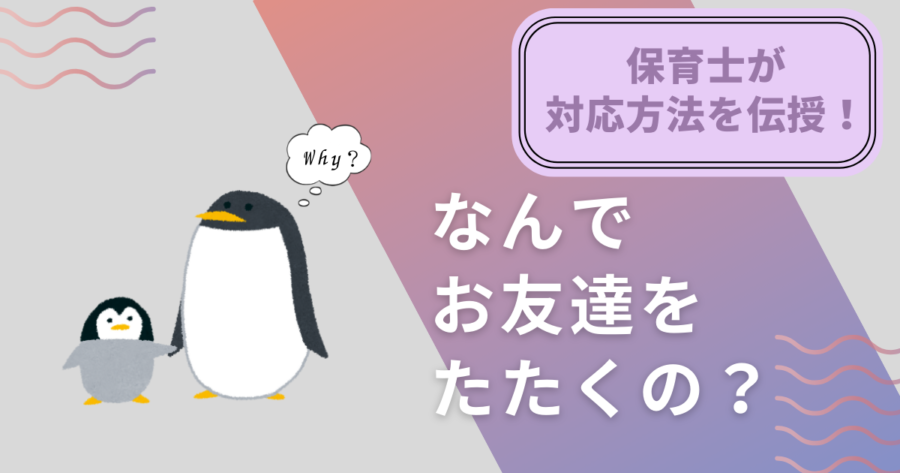
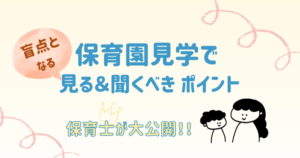
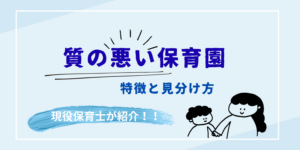
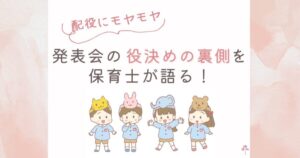
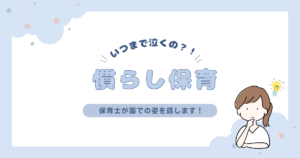
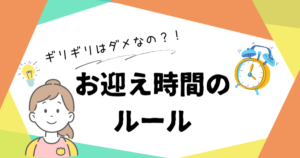


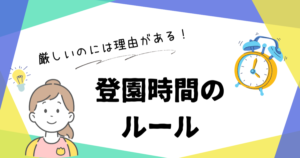

気軽にコメントもお待ちしています