「スマホって、いつから持たせるべき?」
「中学生になったら、みんなスマホ持ってるの?」
「スマホルールって、どうやって決めればいいの?」
子どもにスマホを持たせるタイミングって、ほんとに悩みますよね。
今やスマホは、”持っていて当たり前” の時代。
でも、ただ持たせるだけでは、トラブルや使いすぎが心配…。
だけど、女子はつながり大切にする分、スマホがないことで仲間に入りにくくなることもあります。
だからこそ、親子でしっかりと話し合い、「わが家のルール」を決めておくことが大切です。
この記事では、高2と中3の娘を育てる姉妹ママのくぅが、
実際に体験した中学生女子のスマホ事情と、親子で決めた4つのルールをリアルにご紹介します。
中学生の娘がハブられないためにスマホを持たせたタイミングは?

わが家の娘たちは、どちらも中学入学前の小学6年生のお正月明けにスマホを持たせました。
中学では、「グループLINEが主流」となっているから
これが一番の理由です。
特に、中学生になると「女子は持っていないと仲間に入りにくい」という、先輩ママからのリアルな声が大きかったですね。
「グループLINEにいないからって、仲間外れにする子となんて、そもそも仲良くしなきゃいいのに。」
———そう思う気持ちもわかります。
でも実際は、意図的に仲間外れにされるというよりも、
「話題についていけず、輪に入れなくなる」ケースが多いんです。
実際、中学生になってからも娘の友達の中には「まだスマホを持っていない」という子もいました。
前日にグループLINEで盛り上がった話題の続きを「あのあとさ~」と話すことがあるそうです。
大した内容ではないからこそ、持っていない子にはわざわざ説明しないので、結果的にその子だけ話に入れず、ぽつんとしてしまうことも。
また、今は遊ぶ計画もLINEで決めるのが主流。
持っていない子には事後報告になってしまい、予定が合わないことが続くうちに、「自分のせいで…」と申し訳なく感じてしまう子もいたそうです。
中には、お母さんのスマホでLINEだけは登録して参加している子もいました。
でも、そのお母さんからは「会話が止まらないと、スマホをずっと取られてしまう」との話も。
『親のスマホを貸す方法』も、意外と現実的ではないと感じました。
わが家は、まずは夫婦でよく話し合いました。
使用料の支払いや、使わせ方など相談し、「準備期間も兼ねて」小学6年冬からスマホデビューさせることに。

うちは、共働きだったこともあり、子どもからの帰宅連絡で安心できたのも、スマホを持たせて良かったポイントのひとつ。
そして、持たせる前にきちんと子どもと話し合ったのが「スマホを使うルール」。
ここからは、その4つの約束を詳しくお話しますね。
中学生のスマホルール~わが家の場合~
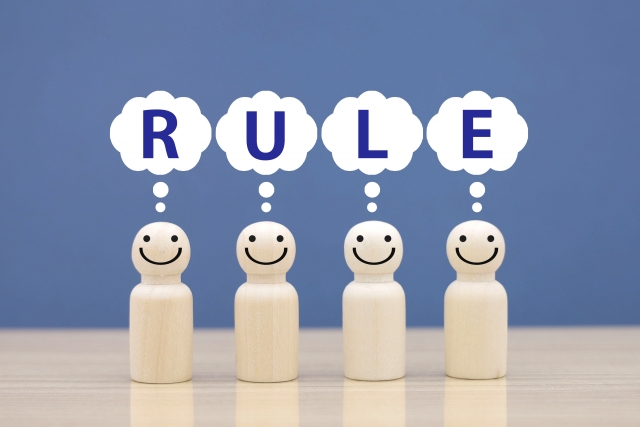
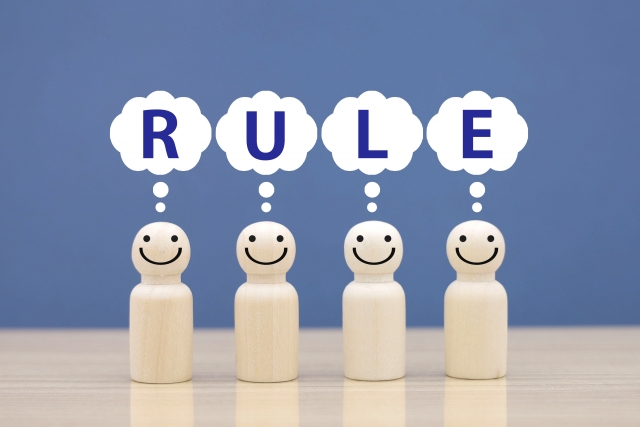
子どもにスマホを持たせる前に、まず伝えたのは、
「スマホはおもちゃではない」ということ。
本体を買うにも、使うにもお金がかかるということを、しっかりと伝えました。
親が支払ううちは、「ルールの中で使う」ことを約束してほしい。
それができないなら、スマホは買わない。
まずは、娘にこの“約束を守れるかどうか”の確認をしました。
そして、そのうえで使用ルールを一緒に決めました。
わが家の携帯ルール
・2階には持って行かない(使うのはリビングのみ)
・使用時間は毎日20時まで
・ギガは3GBまで
・アプリは入れる前に相談(勝手に入れない)
「使う時間」と「使う場所」をしっかり区切ったのは大成功!
ルール① 使用場所はリビングのみ!
リビング限定にしたことで、『何をしているか見える安心感』がありました。
もちろん、トイレやお風呂にも持ち込みは禁止。
ただ、電話だけは相手を伝えたうえで、1時間までなら自分の部屋での使用OKにしています。



さすがに1時間もリビングで話されたら、うるさいですしね~
ルール② 使用時間は20時まで!
使用時間を「20時まで」と決めたことで、それ以降は勉強に集中したり、家族で過ごす時間を持てたり…
娘たちにとっても、いい切り替えのタイミングとなりました。
また、友達にも「わが家は20時までしかスマホ使えないから」とと絶えていたようで、それをあかっている友達は、「20時までに連絡しなきゃ!」と意識してくれていたそうです。
そうすることで、「昨日なんで返信してくれなかったの?!」というトラブルも回避できますね。



周囲にもルールを伝える大切さを、親としても学びました。
ルール③ 通信量は3GB!
さらに、ギガ数を3GBに設定したのも、あえての工夫。
外で動画を見たり、SNSを使いすぎたりすると、あっという間に通信制限がかかってしまいます。
その「限られた容量」のなかでどう使うかを自分で考えることが、『時間とお金の自己管理』を学ぶきっかけにもなりました。
自分たちで考え、使い方を工夫するようになったのは、少ないギガ数にしたからこそですね。
ルール④ アプリ入手は親判断!
なんでもかんでもアプリを入れるのは危険なので、「勝手に入れない」ことを約束。
長女はdocomoのU15で契約したので、「ドコモ安心フィルター」というものをすすめられ、加入したのですが…
これが、本当に面倒で!
もちろん、変な広告も表示されないし、検索もきちんと制限されます。
でも、LINEやインスタなどのアプリDLの際には、色々と解除したり設定したり…親の私が面倒でやめました(笑)
それからは、子どもにアダルト系やら誘惑系の話をし、「自己管理」という形に切り替えました。
中学生のスマホルールを決めた目的
このように、あいまいにせず、最初に明確なルールを決めたことがポイント。
娘たちも「約束の範囲で使う」という意識を持てたように感じています。
また、このルールには「安心してつながるため」という目的もあります。
特に女子は、小さな頃から「○○ちゃんと一緒」という意識が強いです。
私が受け持っているいる3歳児でさえ、すでに女子特有の関係形成はうまれているくらいですから。
中学生になると、女子同士のつながりは”スマホの中”にも広がります。
「スマホを持つ=仲間の輪に入るチケット」のようなもの。
だからこそ、「ハブられないために持たせる」ではなく、
“安全に・安心してつながるためのルール”を一緒に作ることを意識しました。
親が心配だから制限する、というより…
「あなたが安全に楽しむためのルールだよ」と伝えたことで、娘たちも素直に受け入れてくれました。
ルールをつくるだけじゃなく、家族で共有する工夫もしています。



ちなみに、わが家では「スマホ=共有ツール」としても使っていて、
家族全員でLINEはもちろん、BeRealやTimetreeを活用してるよ。
高校生になってからのスマホルールの変化
長女は現在高校2年生(2025年当時)。
高校進学をきっかけに、時間制限は解除しました。
そもそも、部活終わって家に帰るのが21時前なので、以前のルールのままでは現実的に難しかったんです。
ただし、「リビングで使用する」というルールは継続中。
お風呂・トイレ・寝室への持ち込みは禁止のままです。



わが家は、子ども部屋があるものの、勉強もリビングでするので、ほとんどリビングで過ごしているっているのも大きいと思います。


電話だけは、相変わらず例外アリ。



電話つないだまま、友達と一緒に課題していることとかあって、面白いよね~。これも時代ですね。
通信料(ギガ)は5GBに増量しました。
高校生にもなると、20GBや無制限にしている家庭が多いようですが、とりあえず5GBで様子見。
週末の予定や文化祭が重なった月はさすがに足りず、1GB買い足してあげたこともありました。



文化祭で使えないのは、さすがに可哀そうだからね~(笑)
それ以外の月は、いまのところうまくやりくりできているようです。
電車通学の際も、動画は事前にDLしておいたり、無料WiFiをうまく利用する。
中学時代からの「上手な使い方の工夫」が活きています。
高校生になってもやはり、「スマホ代は親が払っている」という意識を持たせておくことが大切ですね。
まとめ|ルールを守ることで親子の信頼を築く


中学生は、スマホで世界が一気に広がる時期です。
「持っていないと仲間外れになるかも」
———そんな女子のリアルも無視はできませんよね。
まずは「スマホはおもちゃではない」という意識を持たせたうえで、
「ダメ」と制限するより、「どう使うか」を一緒に考える姿勢が大切です。
私たち親が過ごしてきた時代とは、スマホによって取り巻く環境がまるで違います。
だからこそ、親も柔軟にアップデートしていくことが必要です。



私が高校生の時は、ポケベルが主流。
休み時間のたびに公衆電話に並ぶ生徒が多すぎて、「#」が使えないようにつぶされました(笑)
スマホは、上手に使えば日々の生活や学びを支える便利なツール。
トラブルが怖いからこそ、ルールを明確にし、お互いを信頼して使える関係を築くことが大事です。
「信頼して任せてもらえる」経験は、子どもたちにとっても大きな自信になります。
そうした積み重ねが“つながりを大切にできる力“へと育っていくのだと思います。
親の私も使いすぎに注意しながら、うまく使っていきたいです。
▶姉妹育児をしていると、同性だからこそぶつかることあるんですよね。
そんな大変だったころの姉妹育児のこと、書いてます。よかったら合わせて読んでみてください。
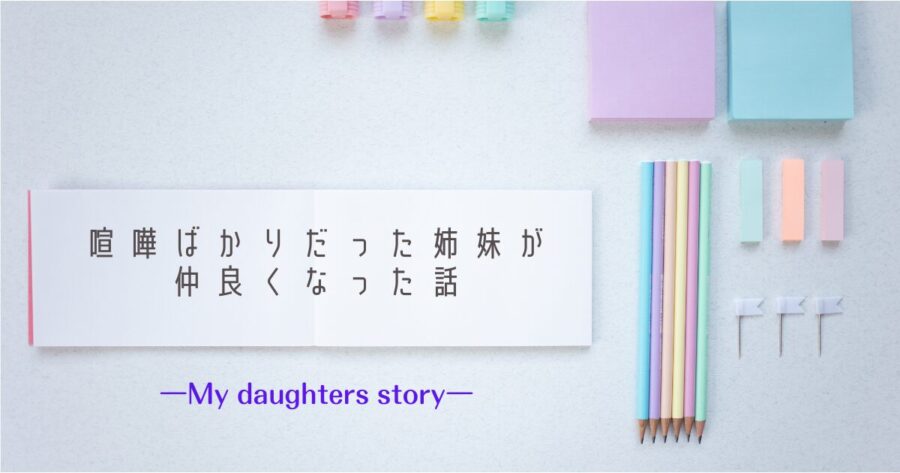
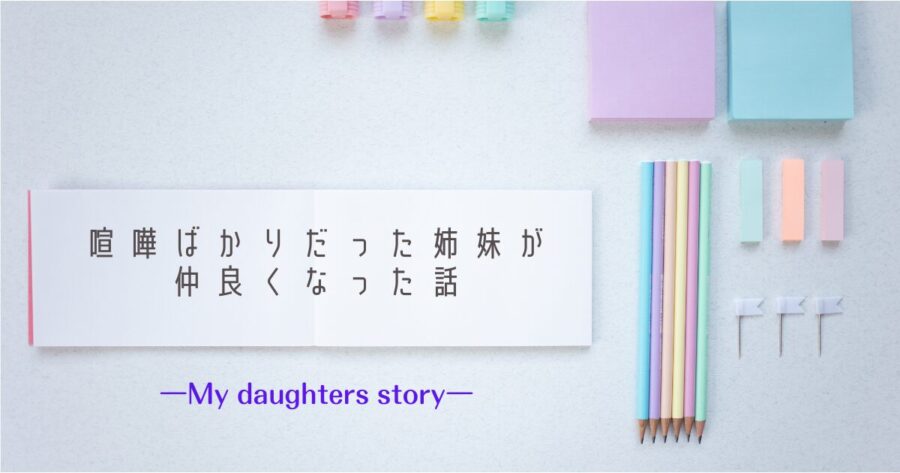
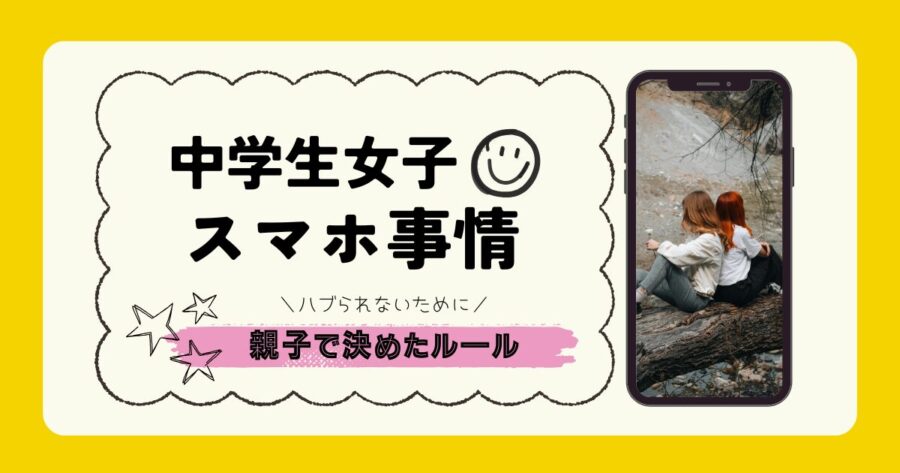


コメント