「なんでうちの子、この役なの…?」
発表会の配役を聞いて、少しモヤッとしたこと、ありませんか?
パパ・ママが「どうして?」と思うのと同じくらい、
実は保育士も
「どうすれば 全員が納得できるのか」
そう悩んでいます。
それくらい、配役決めは本当に難しく、
神経を使うものなんです。
この記事では、
現役保育士の立場から配役の決め方と、
その裏にある本音をお伝えします。
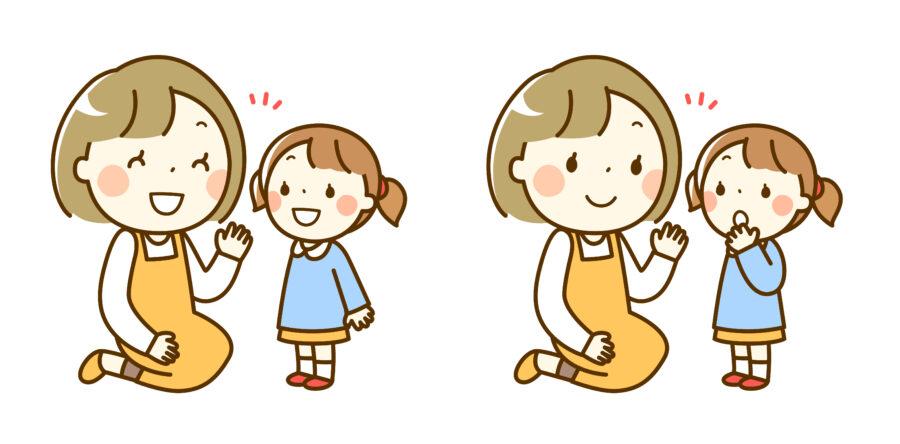
広告
なぜ発表会の配役で不満が出るのか?
まずは、なぜパパ・ママが不満に思うのかを考えてみましょう。
思っていた役じゃなかった
出番が少ない・セリフが短い
衣装が地味でかわいくない
パパ・ママからすれば、
やはりわが子の頑張る姿は、
1秒でも多く見たいものですよね。
また、
・ママ友の子どもとの役柄を比べてしまう
・SNSで可愛い衣装を着ている子を見る
そうなれば、
モヤモヤはどうしても増えてしまいます。
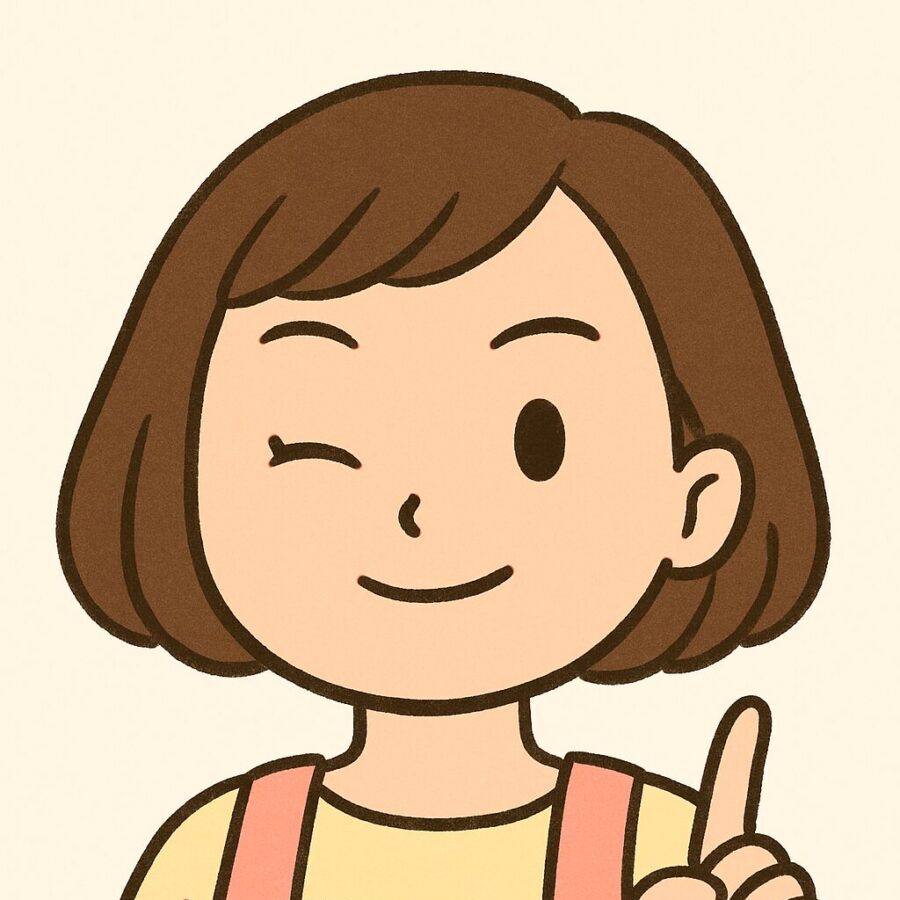
おばあさん役の地味な衣装より、シンデレラのドレスを着ている方が、
そりゃ~可愛く見えますもんね!
「うちの子だったら、もっと台詞が多くて出番の多い役ができるのに…」
子どもの頑張りを見てきたママ・パパほど、
そう感じやすくなるものです。
私自身保育士でもありますが、
親でもありますので、その気持ちは本当によくわかります。
配役の納得できず不満に思うことは、
親としてとても自然なことなんです。
広告
保育士も悩む!迷う!配役決めの裏側


役によって、出番やセリフが多いのはどうしても仕方がありません。
でも、「できる子だから」だけで決めているわけではないんです。
しっかり者の子でも、人前に立つのは苦手な子もいます。
セリフ量が多くて、途中で投げだしてしまいそうな子もいます。
一人では不安だけど、誰かと一緒なら頑張れる子もいます。
それらすべてを考慮して、
配役決めは慎重に進める必要があります。
「発表会」という大きな行事が、
どの子にとっても成長につながるものになってほしい。
だからこそ、
「やりたい子」
「できそうな子」
「頑張ってほしい子」
———それぞれのバランスを取るのが本当に難しいんです。
もちろん、どの子のやりたい気持ちは大切にしています。
でも、最初に希望した役にならなくても、
その役が「やらされた役」にならないようにすることを何より大事にしたいんです。
複数担任であれば、
担任同士で意見が割れることもあります。
そんなときには
お互いの意見・考えを言い合い、
とことん話し合います。
そうすることで、
自分だけでは見えなかった子どもの特性が
見えてくることもあるんです。
また保育士からすると、
「少し荷が重くないかな?」と思う役に挑戦したい子もいます。
「どうしても○○がやりたい!」としっかりとした意思があるときは、
その役の話を丁寧にして、最後までやりきれるかどうかを一緒に確認します。
・子ども同士の関係性
・クラス全体の雰囲気
・その子の特性
これらをしっかり考慮しながら———
少ないセリフでも「このひとことを大事に言えるようにしよう」と、
担任は、一人ひとりの舞台の上で頑張る姿を思い浮かべながら、配役を決めています。
保育園・幼稚園の先生はどうやって配役を決めているの?
配役を決めるまでには、実はたくさんのステップがあります。
まずは劇の題材選びから。
クラスの雰囲気や子どもたちの様子を見て、どんな物語なら無理なくみんなで楽しめるのかを考えます。
繰り返しのやり取りが多いものがいいのか
(例:おおきなかぶ、てぶくろ)
全員が一斉に出てくるものがいいのか
(例;7ひきのこやぎ、さるかに合戦)
クラス人数と、役の数を照らし合わせながら検討していきます。



園によっては「1人役は一人」というところもあります。
逆に「主役が何人もいる」という園もあります。
私は、どちらも経験していますが、1役複数の方がメリットは多いですね。
そのうえで大切なのは、
「この役は誰ができるのか?」ではなく、
「この子にはどんな役が合っているのか?」
という視点。
主役のように出番の多い役が必ずしも、
その子にとっての”いい役”とは限りません。
セリフが多いことが、
プレッシャーになる子もいますから。
まずは、物語を理解させ、
役ごとの魅力を伝えることから始めます。
「この役は最初しか出てこないけれど、セリフが多くてちょっと難しいことばもあるの」
「この役はセリフは少ないけど、踊りがあって楽しいよ」
「この役は元気いっぱいのキャラクターだから、大きな声で元気よくセリフが言える子にやってほしいな。」
こうして説明することで、
子どもたちは、
「自分はどの役ができそうかな?」
「どの役をがんばろうかな?」
と考えるようになります。
話すときに少し 誘導ワード をいれることで、
保育士が思い描く配役と、子どもの希望が自然と一致することも多いんです。
それでも、どうしても偏ってしまう場合には、
一人ひとりとじっくり話します。
決して、「先生が決めたから」ではなく、
自分で選んで決めた
という納得感を持って取り組めるように。
セリフの量や出番の多さだけでなく、
その子の性格・得意・苦手・頑張りたい気持ちを踏まえて、
役は決まります。
確かに物語によっては
「主役」「脇役」と呼ばれる立場があります。
でも、保育士はそうは考えていません。
保育園や幼稚園の発表会は、
『みんなが主役』です。
それぞれの役を自分なりに演じきることで、
子どもは自信を持つことができます。
保育士は、全員が舞台の上で輝ける形を目指しているんです。
配役にモヤモヤしたときに知ってほしい3つの考え方
発表会の配役を聞いて「どうしてこの役なの?」と感じること、ありますよね。
でも、そのモヤモヤの裏側には、
実は子どもたちの成長や、
先生たちの深い意図が隠れています。
ここでは、少し気持ちがラクになる3つの視点をお伝えします。
子どもは「自分の役を通して」ぐんと成長する
「主役=いい役」というわけではありません。
子どもにとっては、
どの役も自分が頑張れる大切な役なんです。
「面白そうだから」
「衣装がかわいいから」
「○○ちゃんと一緒がいいから」
———子どもにはその役を選んだ理由は、
大人が思うよりずっと素直で純粋です。
そして、
どの役でも意欲をもって取り組む中で、
セリフを覚えたり、
人前で声を出したり、
友達と協力したりと、
たくさんの成長が見られます。
発表会を終えるころには、
役の大小に関係なく、
どの子どもも大きく成長しています。
本番までの本番までの時間が宝物
保護者が見られるのは、ほんの数分の本番。
でも、保育士たちは毎日の練習の中で、
子どもたちが少しずつできるようになっていく姿を見ています。



昨日より大きな声が出てたよ!
友達のセリフまで覚えて一緒に言っていたね~
失敗しても泣かずによく頑張った!
そんな小さな成長が、
子どもたちにとっては大きな自信の芽
となります。
発表会は「うまくできたかどうか」だけではなく、ここまで頑張ってきた時間を、たくさんの人に見てもらう日なんです。
他と比べるより、わが子らしさを見つけよう
発表会の日、どうしても他の子と比べてしまう瞬間ってありますよね。
でも、子どもたちは「○○ちゃんより上手にやりたい」と思って演じているわけではありません。
保育園・幼稚園の発表会は、「みんなで一つの作品をつくる場」です。
先生たちは、一人ひとりがその子らしく輝ける瞬間を大切にしています。
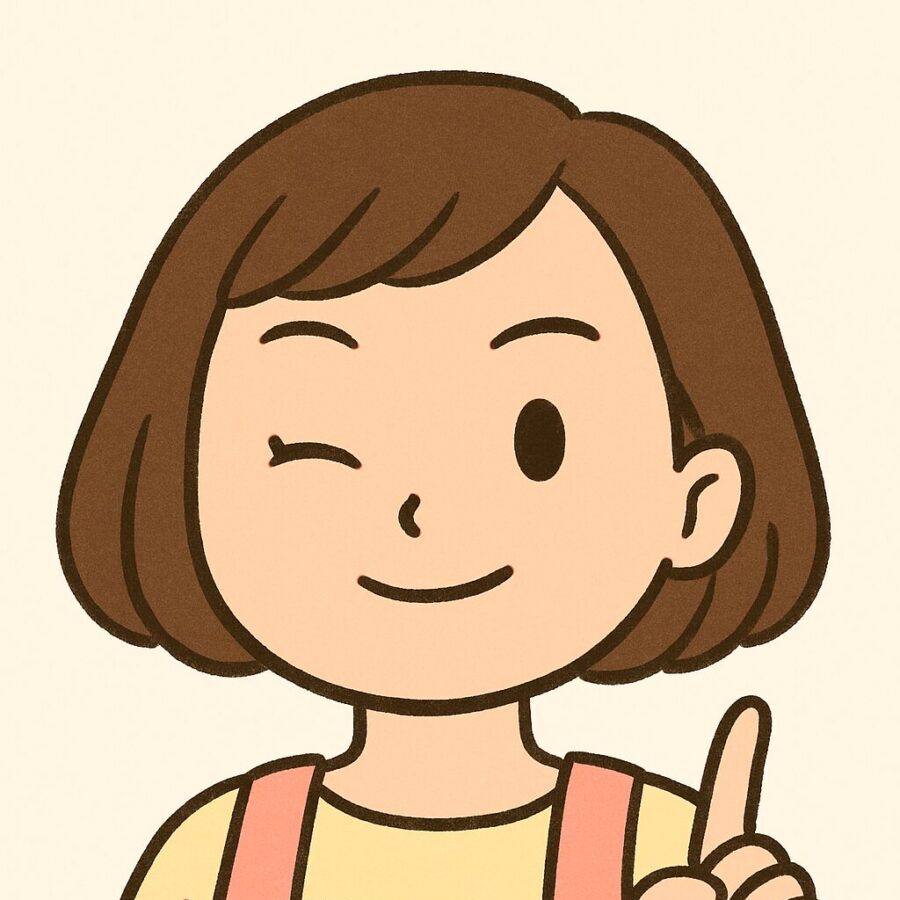
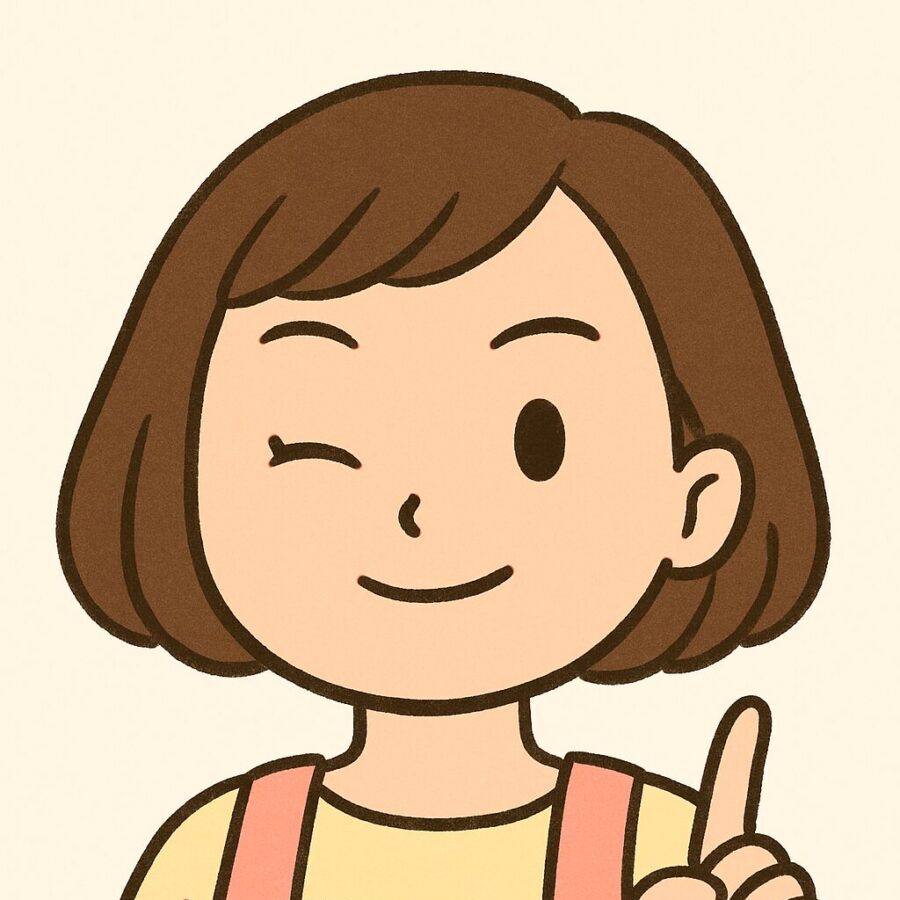
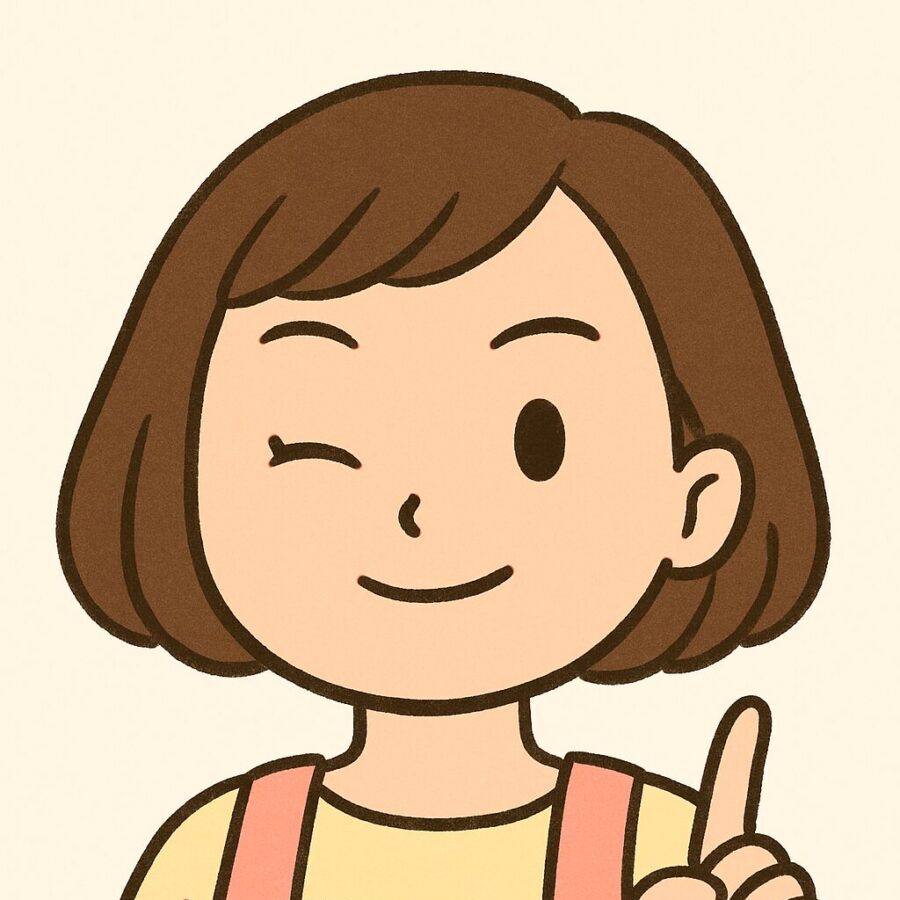
発表会まで、「みんなでがんばろうね。」「みんなで素敵な発表にしようね。」と何度もよく話しています。
セリフが短くても、踊りが少なくても、
その子の表情や仕草にその子しか出せない魅力が詰まっています。



「○○ちゃん、あのセリフがちゃんと言えた…泣」
「忘れずにしっかり移動できた~!」
本番は、裏で感動して泣いてる保育士多いんですよ(笑)
モヤモヤを感じたときこそ、
「うちの子らしく頑張ってたな」と、
温かい目で見てあげてくださいね。
それでも気になるときの、先生への伝え方
子どもが家で
「本当は○○がやりたかったのに、言えなかった…」
「先生が勝手に決めたから、やりたくない。」
こんな言葉を口にすること、ありますよね。
そんなときは、モヤモヤを抱えたままにせず、
先生にやわらかく伝えてみるのがおすすめです。
感情よりも確認の気持ちで話してみよう
「家でこんなふうに話していたんですが、園ではどんな様子ですか?」
そんな聞き方なら、
先生も状況を丁寧に説明しやすくなります。
…というのも、園では子どもが納得して決めたのに、
家に帰って話したりしていると
「やっぱりこっちがよかった」と気持ちが変わることもあるんです。
保育士としても、
「えっ、そんなこと言ってたの?!」
と驚かされることがあります。
だからこそ、まずは子どもの言葉の背景を
先生と共有することが大切です。
伝え方ひとつで、先生との信頼関係が深まる
「どうしてこの役なんですか?」よりも、
「どんな思いで、うちの子はこれを選んだんでしょう?」
「この役になった決め手はなんだったんでしょう?」
そんな聞き方なら、
先生も経緯を説明しやすくなります。
ただ、感情的になることは避けましょう。
冷静に尋ねることで、
先生の意図や子どもの成長ポイントに気付けることが多いですよ。
子どもの気持ちの味方でいてあげよう
「ママはこの役の方がいいと思うよ」
そんなふうに伝えてしまうと…
子どもは、
「ぼくが選んだ役はダメなのかな?」
と感じてしまいます。
子ども自身が選んだ気持ちや、頑張ろうと思っている気持ちを尊重してあげましょう。



「○○にばっちり合ってる役だね!ママ、楽しみにしてるね!」と伝えてあげると、子どもは全力で頑張れますよ。
そして、先生とママ・パパ、みんなが応援してくれることで、子どもは安心して取り組めます。
それが、発表会を通して子どもが自信をつける一番の近道なんです。
広告
まとめ|配役は子どもが育つきっかけのひとつ


発表会の配役は、子どもの性格・得意・苦手を考えながら、
「どの子も輝けるように」
という思いで決めています。
目立つ役だけが「いい役」なわけではなく、
子ども一人ひとりにとって
「今のその子にぴったりの役」があります。
その役をやりきった経験で得た自信は、
必ず次の成長につながります。
もし、モヤモヤした気持ちが出てしまうときは、「子どもの気持ちを理解したい」という気持ちで先生に話してみてください。
ママ・パパと先生が
同じ気持ちで見守ってくれることで、
子どもは安心して発表会に臨み、
本番では自信に満ちあふれた最高の表情を見せてくれます。
発表会は、上手にできたかどうかも大切ですが、それ以上に頑張った過程を一緒に喜ぶ日。
子どもの「できた!」を見つけて、一緒に喜びあってくださいね。
▶発表会では定番の桃太郎。この「も~もたろさん、ももたろさん♪」の歌、6番まであるの知ってました?
桃太郎の歌詞には子育てのヒントまで隠れています!



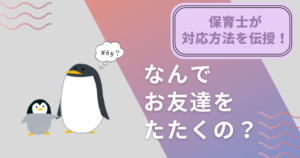
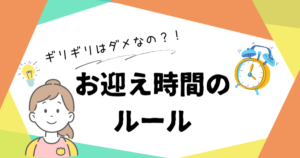
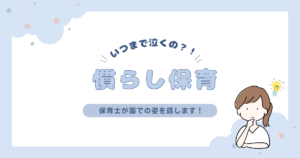
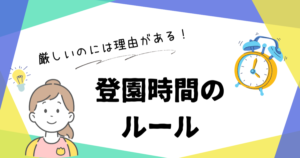

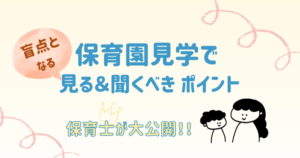
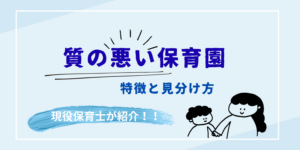


気軽にコメントもお待ちしています