慣らし保育期間で、わが子に泣かれないかと不安になっているお母さん。
すでに慣らし保育期間が始まり、毎日毎日罪悪感を抱きながら、園に預けているお母さん。
「いつまで泣くの?」と、先の見えない不安と戦っていませんか?
安心してください!保育士は、泣かれることには慣れっこです。
そして、ずっと泣いている子はいませんよ。
どーんと先生にお任せしましょう!!
この記事では、現役保育士から、お母さんの気持ちが少しでも軽くなる思考をお話します。
慣らし保育期間が必要な理由とは?

慣らし保育は、子どもが新しい環境に慣れるための準備期間です。
子どもにとって、保育園に入園するということは、とても大きな出来事です。
だからこそ、いきなり1日お母さんと離れて過ごすなんて…未知の物でしかないのです。
自分がいる場所がどこなのか…
自分を抱っこしてくれる人が誰なのか…
お母さんはなぜいないのか…
きっと、不安でいっぱいです。
だからこそ、慣らし保育期間は大切なのです。
子どもたちが、慣らし保育期間を通して、自分の居場所を見つけていくのです。
【保育士が暴露】慣らし保育期間で泣く子の実態4選!

慣らし保育期間が始まり、覚悟はしていたものの、毎日毎日泣かれるとつらいですよね。
きっと罪悪感で、自分を責めてしまうお母さんも多いのではないでしょうか?
でも、安心してください!子どもは意外と楽しんでいますよ。
現役保育士のくぅが、『慣らし保育期間中泣き止まない子の園での実態』をお伝えします!
これを知れば、お母さんの気持ちが軽くなります。
慣らし保育期間で泣く子の実態① どの子もみんな泣きます!
慣らし保育は、子どもにとって、人生初めての集団生活のスタートです。
ずっと一緒だったお母さんと、離れるのですから、泣いて当たり前です!
ママどこいくのぉ?
このひと(保育士)だれなのぉ?
ここは、どこなのぉ?
子ども達の言葉を代弁したら、どんどんでてきちゃいますね。
あなたのお子さんだけではなく、どの子もみんな泣きます!
保育士としては、むしろ泣かない子のが心配になるくらいです。
だから、「慣らし保育期間は、泣くもんだ!」という思考で乗り切りましょう。
慣らし保育期間で泣く子の実態② 子どもは意外とケロっとしてます!
慣らし保育期間が始まり、お母さんと離れるときは泣いてしまう子が多いですが…
ずっと泣いている子は、ほとんどいません!
お母さんがいなくなると、意外とケロっとしているものです。
心配なさらず、気持ちを切り替えてお仕事に励んでください!
子どもは意外とケロっとしてます!
慣らし保育期間で泣く子の実態③ 子どもが泣くのは、お母さんとの絆がある証拠
慣らし保育期間が始まり、もし泣いてくれなかったら、お母さんの方が悲しくなりませんか?
「あれ?大丈夫なの??ほんとに?」なんて、逆にお母さんの方がショックを受けちゃうかもしれません。
お母さんにとっても、初めてわが子を他人に預けるという大きな出来事。
不安や寂しさは、子ども以上に感じて当然です。
だって、これまでずっと一緒に過ごしてきたんですから。
だからこそ、可愛いわが子が他人に預けられて泣くのはむしろ自然なこと。
「よしよし、泣いた泣いた。そうだよね~~。やっぱりママがいいよね~」
と、どっぷりと優越感に浸っちゃってください!
泣かれるのは、お母さんとの絆がしっかりとある証拠。
その気持ちを力に変えて、前向きに乗り越えていきましょう!
慣らし保育期間で泣く子の実態④ 保育士は泣かれることに慣れっこです

毎日泣いてるわが子を預けるのは、保育士さんに申し訳ないなぁ~と感じてしまうと思います。
でも!保育士は、子どもに泣かれるのなんて、慣れっこですから…
全く気にしなくて大丈夫です!
なので、保育士に預けてから、大丈夫かな~と心配でその場をなかなか離れられずにいるお母さん。
保育士側からすると…できれば、さっといなくなっていただけた方がありがたいです。
お子様が、(あれ?泣いてれば帰れる?ママ連れてってくれる?)と思ってしまい、長泣きする子が多いです。
「○○くん(ちゃん)、楽しんできてね! では、よろしくお願いします。」
と、保育士にスパッとお願いしてきましょう。
慣らし保育期間は、親と子の大切な準備期間

慣らし保育は、子どもが新しい環境に慣れる期間であると同時に、保護者にとっても新たな生活を始めるための大切な期間となります。
慣らし保育の期間で、心も体も、新生活に向け、生活リズムを整えていくのです。
慣らし保育の期間は、子どもにとって集団生活の始まり
子どもにとって、保育園はお父さん・お母さんと離れて過ごす初めての場所。
そのため、不安や緊張を感じるのは当然のことです。
だからこそ「慣らし保育」の期間を通じて、少しづつ新しい環境に慣れていく時間が大切です。
中には、人見知りや場所見知りが強い子もいるでしょう。
それでも、保育士やお友だちとの関わりを通して、少しずつ安心して生活できるようになります。
そして、「ここは自分の過ごす場所なんだ」と子ども自身が感じられるようになっていくのです。
慣らし保育の期間は、お母さんも新たな環境に慣れる時間
慣らし保育の期間は、お子さんだけでなく、お母さんにとっても新たな環境に慣れるための大切なステップです。
保育園が始まると、これまでの生活リズムも大きく変わりますよね。
おうちに帰ってから、いつも以上に甘えてきたり、グズグズと不機嫌になってしまうこともあるかもしれません。
そんな時は、「今日もがんばったね。」「ママも一緒にがんばるよ。」と、たっぷり甘えさせてあげましょう。
慣らし保育の期間は、保育士との信頼関係を築くチャンス
慣らし保育の期間は、保育士との信頼関係を築くための大切な時間でもあります。
心配なことや不安に思うことがあれば、遠慮なく保育士に伝えてください。
「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うような、ちょっとしたことでも大丈夫です。
保育士としては、お母さんがどんなことに不安を感じているのかを知ることがとても大切。
お話していただくことで、こちらもより丁寧に対応することができます。
保育士との日々の小さなコミュニケーションの積み重ねが、不安の軽減につながり、自然と信頼関係が深まっていきますよ。
登園時間やお迎え時間など、保育園での“時間の決まり”にも意味があります。詳しくはこちらの記事もどうぞ。
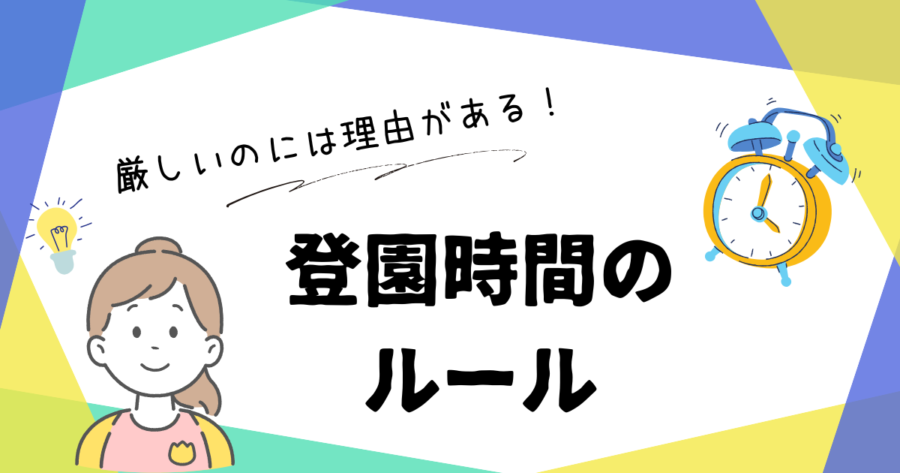
まとめ
うちの子なんでこんなにずっと泣いてるんだろ…と思うお母さん。
いつか必ず、泣かずに行ってくれる日が来ます!
お母さんもそれを信じて、保育士を信頼し、任せてください。
お母さんと離れるときは泣いていても、子どもは新しい環境に順応する能力を持っているのものです。
きっと楽しんで過ごしていますよ。だから、罪悪感を感じることなんてありません。
お仕事が終わってお迎えに行った時には、たくさん褒めて、たくさんスキンシップしてください。
子どもはたくさん褒めてもらえると、「次の日も頑張れば、笑顔のお母さんが迎えに来てくれる!」と思います。
だからまた、次の日も頑張れちゃうんです。
お母さんが笑っていれば、子どもも笑顔になりますよ!
▶童謡桃太郎の歌知っていますか?なじみのあの曲には子育てのヒントが隠されていたんです!

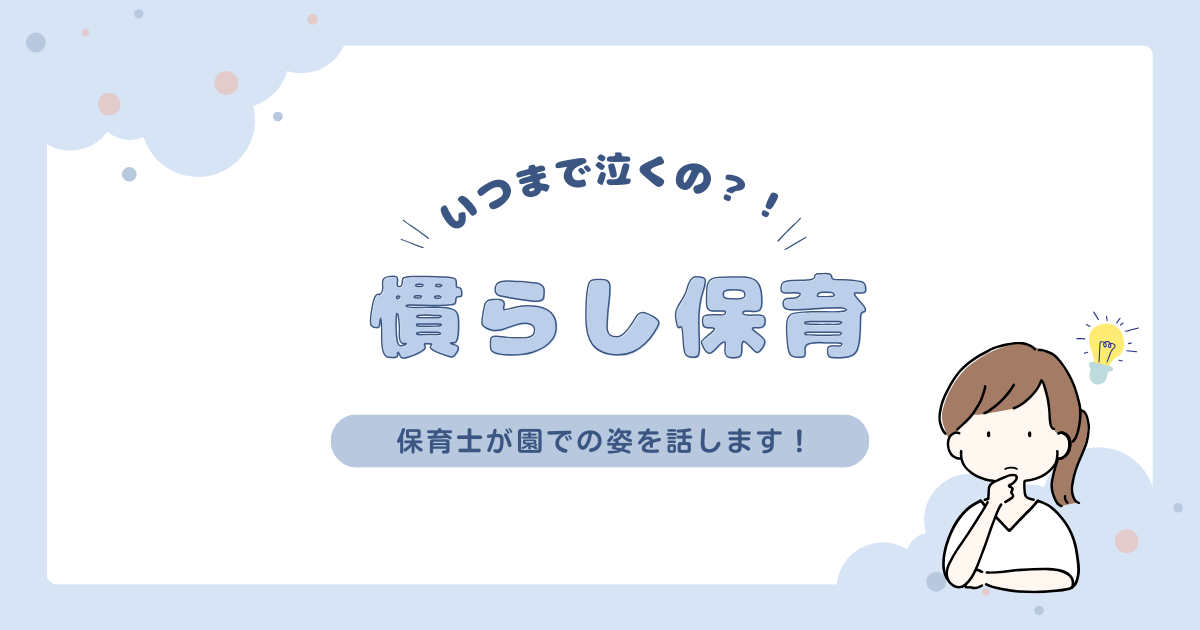

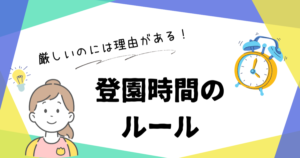
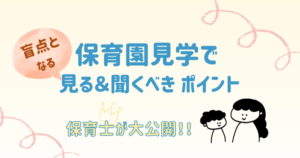

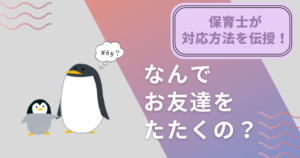
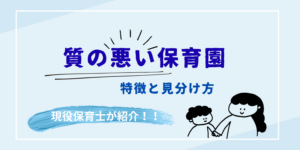
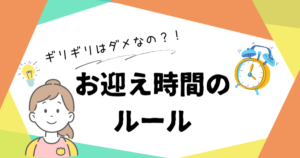
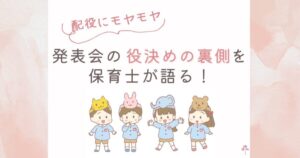

気軽にコメントもお待ちしています