保育の現場では、一人担任よりも複数担任で子どもたちを見ることが一般的になってきています。
「複数担任って本当に楽なのかな?」
「複数の中で、うまくやっていけるかな…」
そう不安を感じてしまう人もいると思います。
確かに、人数が多いからと言って単純に楽になるわけではありません。
仕事は分担できても、人間関係の悩みはどうしてもついてきます。
一人担任を経験した後、複数担任を経験した私だからこそ、伝えられることがあると思います。
複数担任ならではの「壁」や「救い」を、現場で感じたリアルな声として届けます。
\このシリーズの全話まとめページはこちら/


「複数担任って、一人で責任を負わなくていいから、一人担任より絶対ラク!」
そう思っている方、多いのでしょうか?
たしかに、仕事も責任も、みんなで分担できます。
すべて一人でやらなければならない一人担任と比べると、気持ち的には楽かもしれません。
0~1歳児は3対1。(国の基準としては、1歳は5対1ですので、それで対応している園も多いです。)
子どもが20人いれば、職員は7人(国の最低基準は1歳児なら4人体制)になります。
想像してみてください。
子ども20人に、職員7人。それが同じ部屋で1日過ごすのです。
その人数が一部屋にいる——。
なかなかの圧迫感がありますね。
導線を確保するのも大変です。
子どもたちが安心して過ごせるように、動きやすい空間づくりを意識しなければなりません。
また、きちんと役割分担を決め、それを全員が理解して動かないと、保育がスムーズに回りません。
一人担任なら、自分の判断だけでどんどん進めることができますが、複数担任ではそうはいきません。
役割をこなすだけではなく
「私たちが、どんな保育をしていきたいのか」
という根っこの部分をしっかりと話し合い、みんなで共有していく必要があります。
複数で子どもたちを見るということは、コミュニケーションを重ねながら、同じ方向を向いていくこと。
それが何より大切になります。
情報共有は、複数担任の命綱!

複数担任にとって、「情報の共有」がとても大事です。
これを怠ると、保護者からの信頼を失うことさえあります。
なぜなら、保護者にとっては、担任に伝えた=全員に伝わっているという感覚だからです。
それが当たり前。
だからこそ、保護者から受けた伝言は、担任全員が把握していなければなりません。
以前、こんなことがありました。
早番の先生が退勤した後、子どもが少し指を切る怪我をしてしまいました。
でも、どのおもちゃで怪我したのかわからないまま、保護者に謝罪だけしました。
保護者の方は、”同じことがまた起こらないか”を心配していたのに、「怪我の原因」をしっかり伝えられませんでした。
その上、怪我自体はそれほど大きな傷ではなかったため、怪我のことを早番の先生に共有しないまま翌日を迎えてしまいました。
当然、何も知らない早番の先生は、その保護者には何も声をかけることもできず———
結果、
「先生たちは怪我を軽く見ている」
「心配しているのに、何も伝えてくれない」
と、大きな不信感を与えてしまいました。
もちろん、これは私たち担任側のミス。
認識の甘さと、情報共有を後回しにしたため、こんな形で信頼を損ねることになると、痛感しました。
すぐに話し合いをし、
「どんな小さなことでも、その日のうちに全員で共有する」
というルールを改めて確認しました。
今は、グループLINEなど便利なツールもがあります。
だからこそ、
「簡単にできることほど、後回しにしない」
これを徹底しなければいけないのです。
保護者にとって、「先生に伝えた」は、「園全体に伝わっている」と同じです。
私たちも、一語一句、そして相手の気持ちごと受け取って、共有していかなければならなりません。
たとえ自分が直接聞いたわけでなくても、
「どう受け止めるか」が問われます。
不安で相談してくれたのなら、真剣に耳を傾け、
不満を伝えてくれたのなら、受け止め方にも気を付ける。
難しいけれど、困ったときにはみんなで相談し、知恵を出し合える。
それが、複数担任の心強さでもあるのです。
偏る仕事量、気づきが多いと仕事が増える?!

複数で仕事をしていると、残念ですが、どうしても仕事量に差が出てしまいます。
もちろん、書類関係などはきちんと人数分担しています。
でも、日々の保育の中で「気づき」が多い人ほど、自然と動くことが増えていくのです。
たとえば———
「なんか匂うな?」
→うんちをしている子を発見
→おむつ交換をする
「今日、ごみ捨ての日だ」
→ごみを集める
→ごみ収集場まで運ぶ
こんな小さなことの積み重ね。
でも、気付いて行動している人って、だいたい決まったりしています。
気付いてしまったら、見て見ぬふりはできない。
———だって、それが私たちの仕事ですからね。
もし職場でそんな風に頑張ってくれている人がいたら、
「今日は私やりますね」
って、代わってあげるときっと喜ばれるはず。
…でも、これもまた「気づき」。
気づけなければ、そもそも交代するという発想にたどり着けないんですよね。
組む先生次第で、天国にも地獄にも

乳児組だと職員数が5~7人とかになり、完全にチームでの取り組みが重要視されます。
しかし、幼児組は2~3人での保育。
こちらの方の良し悪しを一番左右するのは、やっぱり「組む先生」次第だと思います。
正直、組む先生によって、毎日のしんどさが全然変わる。
「同じ給料なのに、なんで私ばっかり…?」って、モヤモヤすることも、もちろんあります。
でも、それをそのまま相手にぶつけるわけにもいかないのです。
だって、1年間一緒にやっていかなきゃならないのですから。
それ以上に、保育観がズレていることが一番大変ですね。
私は子どもたちとの信頼関係をしっかり築いてから、保育を展開していくことを大切にしています。
しかし、中には、子どもたちとの信頼関係がまだ築けていない段階から、どんどん踏み込んでしまう先生もいます。
また、私が子どもに「自分で考えて答えを見つける力」を育てようとしている途中で、先回りして答えを与えてしまう先生もいました。
逆に相手が、私のやり方に不満を感じ、やりにくく思っていることだってあると思います。
保育のやり方は一つではないので、どれが正解だとかではありません。
だけど、自分の保育が否定されてしまったり、認められてないと感じてしまうと、それは完全に「地獄」ですね。
そうなると、自分の気持ちを我慢して、組む先生に合わせて一年間過ごすことになります。
しかし一方では、同じ保育観で保育ができる先生と組んだ一年間は、本当にやりやすいです。
自分の力だけではできない保育展開が生まれ、子どもたちが飛躍的に成長したりします。
とても学びになるし、子どもたちと一緒に成長している感覚まで味わえます。
毎日が充実していて、保育がとても楽しくできるのです。まさに「天国」ですね。
それでも複数担任でよかったと思える瞬間

コミュニケーションを大切にできる人でなら、複数担任の方が気持ち的には楽だと思います。
私は独身時代に、幼稚園で一人担任を4年間経験しました。
あの時間は、本当に有意義だったし、人生で一番成長した時期だったと確信しています。
でも、結婚して子どもが生まれ、子育てや家庭のことをしながらあの仕事量は、正直…無理です。
だから今は、複数担任で働ける職場を選択しています。
複数担任は、仕事はすべて分配できます。
悩みも共有し、みんなで考えて解決方法を導き出せます。
自分だけじゃないからこそ「気付き」が多く、成長できることも多いです。
でも、忘れてはいけないのは———「人任せ」にしてはいけないということです。
5人いたら、5倍以上の力が発揮できる現場であるべきだと私は思います。
そのために、相乗効果を生み、子どもたちと関われる環境が作られるといいですね。
「誰かがやってくれる」
を待つのではなく、
「私がやる」
と全員が思える状態だったら、きっと、最高の保育ができ、最強ですね。
一人では味わえない手ごたえを感じれたときは、複数担任でよかった!と思える瞬間です。
あなたもそんな瞬間を味わいませんか?
みんなで笑えると、ひとりで笑うよりもっと幸せを感じられますよね。
次回は、一人担任の自由さと大変さ、どちらも抱えた保育士の日々を綴ります。
▶一人担任にメリット・デメリットを語る|30人を一人で見た保育士のリアル


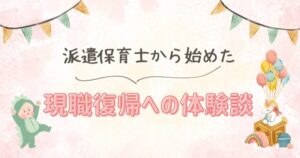






コメント